- 参議院選挙で引っ掛かってみて見えてきたこと -
2025年8月7日'ひと'とITのコラム

第27回参議院選挙が7月3日公示、7月20日投開票で行われました。結果はご存じの通りで、与党が大きく議席を減らす結果となりました。この議席を減らしたことで、野党やマスコミは「国民の自民党離れ」「現政権の退陣が民意」を高らかに喧伝していました。確かに議席を減らし「過半数割れ」という状況になったこと、これは事実です。これにより政治の停滞を招くのではないかと言う見方がある一方、この先、真の政策議論が行える環境になったとの見方もあります。
いずれにせよ、今後の国会運営に対する有権者の選択ですので、その結果責任は有権者にあるわけです。しかし、今の日本の雰囲気だと、この先政治の停滞等が起きたときに、それを時の政権や与党、引いては野党も含めた国会(議員)のせいにしてしまい、有権者自らが選択した結果であることがどこかに行ってしまうのではないかと危惧しています。これでは、なかなか「賢い有権者」への成長は見込めませんね。
今回の選挙、投票率も話題になりました。58.51%、2022年の参議院選挙の投票率52.05%から6%以上伸びました。1980年の参議院選挙では74.54%でしたからまだまだ高い投票率とは言えませんが、昨今の政治離れが叫ばれている中での増加は、それなりに意味ある事実だと思います。
この投票率でもうひとつ話題となったのが期日前投票をする人の増加です。今回の参議院選挙では選挙区で26,182,089人でした。2022年の参議院選挙では19,613,475人でしたから33.5%利用者が増え、衆議院選挙も含めても過去最多を記録しています。また26,182,089人というのは、有権者全体に占める割合が25.27%、投票者全体では43.19%に達します。要は投票した人の4割強が期日前投票を利用しています。この制度が広く認知されたことが投票率に貢献していることは喜ばしいことです。
そもそも"投票日当日に所用等で行けない人"が投票機会を逸しないように制度として拡充されてきた期日前投票ですが、最近は「投票日に行けないわけではないけれどたまたま(期日前投票の)投票所の近くに行くから投票しちゃっておこう」といった人も多く、投票日を指定されることでの"縛り感"から解放されて、行きたいと思ったときに行けるという冗長性が投票行動を促している側面もあると感じます。ただ、法的には「投票日当日に行ける人は、当日に投票する」があくまでも原則のようです。しかし、ここまで利用者が増えて投票率を押し上げる効果も見込めるのであれば、期日前投票という括りをなくし、今回で言えば「投票期間は7月4日(公示日の翌日)から7月20日で、7月20日は最終日なので投票所を増やします。」でも良い気もします。現実的にはすでにそのような感覚で投票行動をしている人も多いのではないでしょうか。そうなると、早々に投票する人は所謂選挙活動にあまり触れないで投票しているわけなので、結局のところ「選挙活動って必要なのか」という疑問につながります(特に日本の選挙カーによる名前連呼や駅前での朝の挨拶に遭遇すると余計感じてしまいます・・・個人の感想です!)。
ただし、期日前投票だと投票後にその候補者が死亡したり、投票後の大きな世情変化などで候補者選定の理由が大きく変わってしまうと、せっかくの投票が無効になったり意図しない一票となるリスクもあるので、「投票の期間化」はそう簡単には実現出来そうもありません。投票機会の拡大の観点では、ネット投票(リモート投票)の実現の方が仕組みの課題解決だけで事が進みそうなので、こちらの方が現実的かもしれません。
さて、先に述べたように「国民の自民党離れ」「現政権の退陣が民意」と言う論調の根拠は議席数の減少です。これを持って「民意は自公政権へのダメ出し」と断じられています。しかし、私の見方はちょっと異なります。確かに、今後の国会運営等を鑑みると、議席数の減少は多くの場面で大きな変化を強いられるのは間違いありません。この意味で「もっと与野党の議論を深めろ!」など今後の国会運営に対する民意が示されたとは言えるでしょう。しかし、「国民の自民党政権離れ」「現政権の退陣が民意」というような民意は本当に示されたのでしょうか?
私は国政選挙後に総務省自治行政局選挙部が出す『選挙結果調』と言う資料を見るようにしています。今回の選挙では『令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙結果調』(https://www.soumu.go.jp/main_content/001021472.pdf)になります。これには選挙時の県ごとの有権者数や投票人数、県別・党派毎得票数、候補者毎の得票数など、選挙結果の全てが事実として記されています。
これを眺めるのは結構おもしろいです。例えば、今回の選挙では全国で選挙区が60,614,869人、比例代表が60,610,666人が投票しました。つまり4,203人が選挙区の投票はしたけれど比例代表の投票はしていない(白票などの無効票ではなく、投票用紙を受け取らなかった)という事実が見えます。全国の投票所は44,758カ所、期日前投票所は6,905カ所でしたので、12.3カ所の投票所で1人の割合となります。これが何を示すのかについての考察には今回は触れませんが、『選挙結果調』はマスコミ等が触れない、いろいろな見方の可能性を拡げる「魔法の調」です。こんなところに「データ駆動型社会」で求められる"データとの付き合い方"の気づきやヒントが隠されている気がしています。
横道から戻りましょう。この資料で党派別の得票数がわかります。今回の選挙で議席を獲得した党派の「得票数」と「当選人数」を表にまとめてみました。
私がなぜこの「得票数」に注目しているのか、まず今巷で騒がれている「民意」、みなさんは「民意」という言葉をどのように定義しますか? 辞書的には【民意:人民の意思(広辞苑7版)】とあります。人民すなわち国民一人ひとりは、さまざまな考えや思想、希望を持っているので国民全員が一致した意思を持つことはまずあり得ません。ならば国民の意思をどのように見える化するのか? これは会議などで結論を導出することと基本的には変わることはなく、多数決という仕組みによって判断することが一般的でしょう。選挙で民意を見える化するのであれば、同様に多数決という仕組みの考え方に則った判断が求められるはずです。では今回の選挙(換言すれば民意の選択)で最も得票数が多かった党派はどこか? 上の表でもわかるように自由民主党です。前回から大きく減らした(選挙区で-6,133,281.316票)とは言え2番目に多かった参政党との差は5,205,732.925票です。すなわち多数決の原理によれば民意は自由民主党のはずです。これは選挙結果の数字が表す事実に基づくものです。しかし、世の中は自由民主党(及び自由民主党の施策)が民意ではないことが明確になったとの論調が渦巻いています。これは、政局絡みの背景を踏まえて大きく得票数が減るという「傾向」を重視すると、そのように見えるのも理解は出来ます。データをどのような背景で、どのような視点で、どのような感情で見るかによって、見えてくる世界が大きく違ってくるという端的な例なのでしょう。
選挙で直接的に競うものは当選=議席ですが、「自公(与党)の過半数割れ」という結果をもって「自由民主党(及び自由民主党の施策)が民意ではない」という一義的な見方にもちょっと違和を感じます。そもそも「議席数」によって見える化された民意は何か? あくまでも国会運営のやり方で、今とは違う国会運営を望んでいるという民意なんだと思います。議席数と党派支持率は別物であると私は感じています。
今回の選挙で最も少ない得票数で当選したのは和歌山の望月良男氏(無所属)でその得票数は141,604票です。逆に落選した候補で最も得票数が多かったのは神奈川の佐々木さやか氏(公明党)でその得票数は571,796票です。すなわち議席だけで見ると571,796人の有権者が佐々木氏及び公明党を支持していると言う事実が消えてしまいます。この辺りは所謂「一票の格差」として選挙のたびに話題となることにつながります。2016年のトランプ氏対ヒラリークリント氏の大統領選挙、アメリカ大統領選挙は各州の選挙人270人獲得すると勝つことが出来ます。この時の勝者はご存じの通りトランプ氏です。しかしこの選挙での得票率はトランプ氏の46%に対してクリントン氏は48%、260万票以上クリントン氏の方が多かったのですが、獲得選挙人数で敗れました。大統領選挙では同様な負け方は5人いるのですが、クリントン氏はその中で最も得票率で大差をつけて勝っていたのに落選しました。何処でも選挙の仕組みはその国の歴史や価値観などによって築かれてきています。日本でも毎回のように話題となる人口の偏りと区割り(参議院選挙では47都道府県の人口分布)に関わる「一票の格差」の大きな課題を抱えながら学んできています。ただし、先述の「有権者の支持数による民意」が何らかの形で反映できないうちは、真の意味での民意が示されることはないのかもしれません。
ちなみに先ほどの『選挙結果調』から次のようなデータが導出できます。
自由民主党:535,927 立憲民主党:607,977 日本維新の会:1,150,611
公明党:793,948 国民民主党:718,065 共産党:2,831,672
参政党:1,323,469
これは「選挙区」の各会派の得票数を当選人数で割ったもの、すなわち当選した人が"背負っている"得票数です。最多の共産党と最小の自由民主党では5倍強の開きがあります。このようにいろいろ「データをいじる」ことで、隠れてしまっている「リアル社会の実体」に興味を持つことも大切だと思います。
選挙絡みでもう一つ気になっていることがあります。それは「いつから選挙(開票)がエンタメになったのか?」です。いつのまにか、特に国政選挙の投票日の20時、いや今はほとんどの局が19時50分には「開票特番」が始まります。日曜のゴールデンタイム、子ども泣かせです。そして最も私が気になることが20時ジャストに起きます。カウントダウンをする局まであります(カウントダウンするほどみんな楽しみにしているのでしょうか?)。開票速報!・・・党派別の当選者数、個々の候補者毎の当選確実、でも開票率0%・・・いやぁ、我々は何を見せられているのでしょうか・・・?
各局とも当然ながら予測が外れることは絶対に避けたいので、さまざまな情報・データの収集や綿密な取材を基に緻密な分析を行っています。今回の参議院選挙の出口調査をNHKとNNN系列30局、読売新聞は共同で行っていて、約20万人規模の有効回答を得ています。これは全国大の数なので、単純に45選挙区で割れば1選挙区当たり約4,500人となります。これはもの凄く手間がかかります。よく新聞社やNHKが「世論調査」を行っています。NHKでは毎回1,200~1,500人の回答数と発表しています。「世論調査」ですから、世論全体の意見すなわち民意としています。だとすると、「1,200~1,500人の回答数だけで日本全体を映し出せているのか」という疑問が湧いてきます。統計をかじったことがある方はすぐに分かると思いますが、日本の人口を1億2千万人と置くと、得られた回答が1億2千万人全体の回答と見なせる"確からしさ"は384人で95%、400人で95.4%、1,066人で97%となります。さらに9,604人の回答が集まれば99%にすることが出来ますが、時間と労力(コスト)も掛かります。バランスを取ると1,000人ちょっとが良い塩梅ということになります。
さて、今回の選挙で20万人以上の出口調査の有効回答を、7時から18時(20時まではやらないようです)の間に集めるのはかなり大変だっただろうと思います。しかし、各局しのぎを削っていて、しかも精度を出来るだけ高めなければならないので、総力を挙げて取り組んでいることが容易に想像できます。ちなみに出口調査で答える有権者が本当のことを言っていることが前提となりますが、昔、私はウソの回答をしたことがあります・・・スイマセン。過去には、ある候補者に当選確実を出して、その候補者の事務所で支援者が歓喜の万歳をしているシーンまで放映したのですが、最終的に落選したというケースが散見されたこともありました。さすがに総務省も黙ってはいられず、行きすぎた開票速報に警鐘を鳴らしました。その後しばらくは当選や当選確実を出すのがかなり慎重だった時期もありましたが、最近の開票速報は各局が秒単位で競っているように見えます。開票速報は報道の世界なので所謂「スクープ」を狙う感性が根にあるのでしょう。私は翌日の朝刊で確定結果(選挙管理委員会の発表)が見られれば充分なのですが、第58回のコラムでも触れたように、人は、待てば分かることは知りたいではなく当てたいという感覚になりやすいのかもしれませんね。確かにグローバルでは、アメリカ大統領選挙やイギリスのEU離脱で争った国民投票などを"賭け"にするブックメーカーも存在しているくらいなので、人という動物の本能なのでしょう。だから結果が気になってしまい、ついつい各局の開票速報の番組をはしごしながら夜遅くまで観てしまうのかもしれません。そこそこ視聴率も稼げるとなれば、局としても力を入れざるを得ません。
ITの進化は、開票速報の精度向上に大きな役割を果たしてきています。先に述べた膨大な情報・データの収集・蓄積・整理、選挙区のさまざまな影響因子の特定につながるビッグデータ、多面的な分析を即座に行うAIなど、最近の「データ駆動型社会」を支える技術が、まさに開票速報を支えています。しかし、ここで一旦立ち止まって冷静に見なければならないこともあります。それは先にも書きましたが「党派別の当選者数、個々の候補者毎の当選確実、でも開票率0%・・・いやぁ、我々は何を見せられているのでしょうか・・・?」。
いま「リアルの世界だけでは解決出来ない課題を、データ活用によるサイバー空間上でリアルだけでは産み出せない解決策(もしくは解決につながる価値)を創出し、それをリアルの世界で現実の解決策として活用していく」ことが大きな流れです。ここで重要なのは、最後はリアルの世界の現実に帰結することです。では開票速報はどうなっているでしょうか? 選挙で開票に関するリアルの世界は各選挙管理委員会が行なう開票作業や、各選挙管理委員会が認定する開票結果であり当選証書です。テレビで見せられている開票結果は、先に述べた各局が独自に集めた情報・データ(選管が途中で発表する開票状況もその一部)を駆使したサイバー空間でのシミュレーション結果です。あくまでもサイバー空間に閉じています。ではこれがリアルの世界に戻るかというと、戻りはしません。最終的なリアルの世界である選挙管理委員会の開票結果は、サイバーの世界のシミュレーション結果が合っていたどうかの答え合わせとして使われるに過ぎません。そして、ITの進化などの効果で、このシミュレーションの精度が飛躍的に向上してきています。この先さらに向上することは明らかです。
片や、リアルの世界で行われている投票~開票という一連のプロセスには膨大なお金と労力が掛かっています。このリアルの世界での課題を解決するために、全国で無作為に選ばれた20万人の回答で当選者を導出することが出来る世界も見えてきます。が・・・みなさんはこれを善しとしますか? しかし、すでに各局の開票速報で「当選」や「当選確実」(この当選確実の意味もよくわかりませんが・・・)が出ると万歳が始まりますし、コメンテーターのインタビューも始まります。すなわち、開票速報というサイバーの世界からリアルの世界に戻ることを忘れてしまっています。既に我々は未知の領域に知らず知らずのうちに入り込んでいることを認識する必要があるのではないでしょうか。
7月に実施した新聞やテレビ局の世論調の多くで、石破さんは「辞めるべき」よりも「辞めなくても良い」の方が高い結果となっています。リアルの世界だけでも混沌としている昨今です。
〔本コラムは偶数月の10日頃更新しています。〕
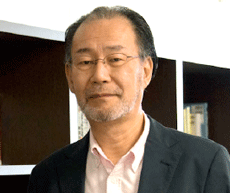
技術士(電気・電子部門)
永倉正洋 技術士事務所 代表
一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事
1980年 日立製作所入社。 システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。
2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。
2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。
2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。
2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。
2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。
2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。
2020年 日立アカデミーを退社。
永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。
お問い合わせ