- 脳のコンピュータと"道具"のあり方の一例 -
2024年6月10日'ひと'とITのコラム
人間が脳内で行っている、計算するという機能を道具に置き換えた、算盤(そろばん)と電卓。一方で、今注目される生成AIに代表されるデジタル(IT)は、「人間が行っていることを出来るだけ置き換える"道具"」ではなく「人間を置き換える"道具"」という側面も見えてきました。デジタル(IT)の進化は止められません。人間とデジタル(IT)が共存していくために、私たちは今後デジタル(IT)をどのように使い熟していくべきでしょうか。今回のコラム『デジタル(IT)は算盤(そろばん)を生み出せるか?』で考えてみましょう。 (コラム担当記)
今回のテーマに入る前に、以前書いたコラムの後日談を。
『第56回 情報のバイアスの源 - 最近 モヤモヤしていることからの考察 -』で、今年の1月2日に羽田空港で起きた日本航空機と海上保安庁機との衝突事故を一例に、『なぜ、人は憶測による犯人捜しが好きなのか・・・モヤモヤします。』と書きました。その後3月になって大きな(関心度が高い)ニュースが駆け巡りました。ドジャース大谷投手の元通訳である水原氏が、後日銀行詐欺容疑で訴追された事件です。当初この事件の中味だけではなく、「あれだけの金額を口座から引き出すためには、水原氏単独では無理なので大谷選手も知っていたのではないか」といった憶測による主張も散見されました。その後米国連邦捜査局(FBI)の声明で水原氏の単独犯行であることが明らかになることで、「大谷選手が関わっているはずがない」という主張をしていた人たちから「大谷選手を少しでも疑った人は謝罪すべき!」といった怒りにも近い主張が噴出しました。この時私は「情報が少なく、何も判断できない状況で大谷選手が関わっている/関わっていないという判断をすることそのものがおかしいのであって、ある意味たまたま関わっていないという主張が"当たった"だけでしょ! ドヤ顔で謝罪しろ!なんて言えないんじゃない?」と感じていました。そう、これも『なぜ、人は憶測による犯人捜しが好きなのか・・・モヤモヤします。』です。これについて先日ネット記事を覧ていたら、国際政治学者の三浦瑠麗氏が面白い視点の発信をしていました。三浦氏は『世の中には根拠のない臆測がしじゅう飛び交いますが、待てばわかることを拙速に疑ったり中傷したりするのは、これまた一歩先の未来を知りたがる人間のさがゆえ。当たったら喜び、外れたら罪悪感から慌てて知らんぷりをしたり、弁解する。正直、その人が外したか当てたかはどうでもいいことですが、本人は気になって仕方がないのですね。これがギャンブル。他の人間の人生がかかっている問題で、勝手にギャンブルしている人たち。これが大谷翔平さんと水原一平さんをめぐる騒ぎの本質です』と述べていました。「なるほど!この視点があるかぁ!」と思ったのが『待てばわかることを拙速に疑ったり中傷したりするのは、これまた一歩先の未来を知りたがる人間のさが』のくだりです。確かに一歩先の未来を知りたがることは結構多い気がします。例示した羽田の事故やさまざまな事件の犯人捜しの類いだけでなく、「次の電車、混んでいるかどうか当ててみようぜ!」的な日常の会話、推理ドラマや推理小説、競馬や競艇などでもお金を掛けるのではなく"当てる"事が楽しみという人も多くいます。『なぜ、人は憶測による犯人捜しが好きなのか・・・モヤモヤします。』に対する正面からの答えではないのですが、"憶測"だから好きなのでしょう。要は、"識りたい(知りたいではない)"のではなく"当てたい"という感覚ですね。"当てる"というのは、情報が多い状況よりも少ない状況の方が、より"当てた感"が強くなります。情報が多いと"当てる"というよりは"分析して推測する"という領域に入ります。情報リテラシー的には、情報が少なければ推測するべきではないのですが、少ない情報で"当てる"ことが好きなのであれば、情報リテラシーもへったくれも無いということです。違った意味でモヤモヤすることが増えました・・・
さて、算盤(そろばん)・・・ みなさんは使えますか? 子どもの頃習っていたとか、「公益財団法人全国珠算教育連盟(全珠連)」や「日本商工会議所(日商)」の検定に合格しているという人もいるでしょう。ちなみに私は小学校で習いましたが、からっきしダメでした。珠を置くだけで精一杯、"使う"レベルまでは到達しませんでした。自分の算盤(そろばん)と友人から借りた算盤(そろばん)を床の上に逆さにし、「スケート!」と称して上に乗るという違った意味で"使う"ことをしました。結果ひっくり返って頭を床に打ち付け、先生にこっぴどく叱られた苦い思い出が60年ぶりに蘇ります・・・
さて、算盤(そろばん)というと「玉が串ざしになって桁ごとに整然と並んだ計算のための道具」をイメージします。広辞苑でも 『そろばん 【算盤・十露盤】 ①計算器の一種。横長浅底の箱あるいは枠に横に梁を設け、これを貫いて縦に渡した多くの串に5個ないし7個の珠(たま)を貫く。珠は梁上に1個(もしくは2個)あって1個で5を表し、梁下に5個(現在では主に4個)あって1個で1を表す。この珠を上下させて計算する。中国で宋末から元代に行われ、日本へは室町末期頃伝来したと推定される。』とあります。ところが同じ広辞苑に『さん‐ばん 【算盤】 ①「そろばん」① に同じ。②算木をその上に並べ、計算をするための盤。木・布・紙などで作り、盤面に縦横の碁盤目を引き、算木の配列や数値の位取りを明示するのに役立てる。』ともあります。古代の算盤(そろばん)には、メソポタミア地方で4~5000年前に土や砂の上に線を引き、そこに小石を置いて使う「土砂そろばん(Dust Abacus)」や、エジプト・ギリシア・ローマなどで2500年前に岩や木の平盤の上に位取りの線を引き小石や銅貨を置いて使う「線そろばん(Line Abacus)」などが存在していたようです。すなわち、算盤(さんばん)が石を並べて計算をするための平らな板(石とか木でできている)のことをいい、算盤(そろばん)が算盤(さんばん)と石が組み合わさった計算のための道具を示しています。もともと人類の歴史で数を表したり計算をするということは難しく、それを分かり易くするために生まれたのが算盤(さんばん)であり算盤(そろばん)ということです。小学校から算数で計算を習いますが、基本的には算盤(そろばん)などの道具を使わずに紙と鉛筆と脳だけを使っています。これって、人類の進化の過程で難しいとされてきたことをやらせているわけです。
算盤(そろばん)は、人類の進化の過程で長年の工夫の結果手に入れた「計算のための道具」ですが、人類史上でごく最近手に入れた「計算のための道具」として電卓(電子卓上計算機)もあります。初めて電卓を手に入れたときは、出た答えを疑っていたことを思い出します。何しろ「機械が計算する」なんてことは人生で初めての経験です。「人よりも機械の方が頭が良い?!・・・俄には信じられませんでした。だから電卓で計算しても紙と鉛筆と脳で確かめていました。そんな中、手で計算してみると答えが違っていたことがありました。手計算を3度やり直してもやはり自分の答えが正しいので、「やはり機械は信用ならない!」と思ったのですが、結局は電卓の打ち間違いで電卓に「疑ってごめんなさい!」でした。
さて、算盤(そろばん)も電卓も「計算するための"道具"」ではありますが、根本的に違うことがあります。電卓を使うと、"計算する"という脳の機能は使いません。数字を正しく入力し、キー(ボタン)を適切に押下することだけですべてが終了します。人が筆算するよりは確実・短時間・正確に計算を為し得ます。「人間の脳が行っている計算という機能を全面的に置き換える"道具"」であり、効率化を軸とした利便性向上という価値を得られます。では算盤(そろばん)はどうでしょう。算盤(そろばん)が全く使えない人間が説明するのも気が引けるのですが、算盤(そろばん)を使った計算方法整理してみます。まずは普通の筆算。例えば123+456を計算するときを考えてみると、〈一の位〉⇒〈十の位〉⇒〈百の位〉 の順で計算していきますよね。すなわち〈(一の位の)3+6〔=9〕 〉⇒〈(十の位の)2+5〔=7〕 〉⇒〈(百の位の)1+4〔=5〕 〉と各位(くらい)を計算して、出た答えを位順に並べ替えて579と導き出します。486+789のように"繰り上がり"が発生する場合も繰り上がり分を上の位に加えるだけで同様です。文章だと分かりにくいかもしれませんが、計算式に置き換えると至極単純なことです。これをよく見てみると、各位(くらい)に分解することで、基本的に一桁の足し算を繰り返しているに過ぎません。計算力の計算そのものは一桁の足し算で、子どもの頃にドリルなどを使って行った反復学習による"暗記"で脳内に蓄積しています。すなわち暗記している一桁の計算結果を、位ごとに呼び出して紙に書き留めることを繰り返しています。ちなみにコンピュータは人間では到底不可能なレベルの複雑な計算を短時間に行いますが、コンピュータの中核であるCPU(Central Process Unit)も基本は足し算しか出来ません。四則演算とは言いますが計算という行為の"原子核"は足し算ということになります。では算盤(そろばん)を使った場合はどのように計算(珠算)しているのでしょうか。筆算が紙と鉛筆を用いて行うのに対し、こちらは算盤(そろばん)を使います(だから珠算なのですが・・・)。算盤(そろばん)の珠を動かすことだけで計算しています。筆算の場合に存在していた、暗記している一桁の計算結果を呼び出すプロセスが存在しません。なので珠の使い方を身につければ素早く計算出来ることになります(私は使いこなせないので、"計算出来るらしい"としか言えないのですが・・・)。ここまでの話しだと、算盤(そろばん)も電卓と同様に「人間の脳が行っている計算という機能を全面的に置き換える"道具"」に見えます。しかし、算盤(そろばん)はこれで終わりません。 算盤(そろばん)を使いこなしている多くの人が、暗算がめちゃくちゃ速いことはよく知られています。テレビなどでもたまに取り上げられています。しかも暗算中に話しかけても、その受け答えをしながらしっかり計算をしている。神業に思えます。ちなみに海外で二桁以上の計算を暗算で行うと「ミラクル!」と言われることも多いと聞いたことがあります。なぜ、珠算を熟すと暗算が早くできるようになるのか? さきほど珠算は『算盤(そろばん)の珠を動かすことだけで計算している』と書きました。算盤(そろばん)の練習を繰り返していると、珠という具体物の動きを脳内では画像処理(イメージ)で捉えるようになります。すると暗算をするときにも、脳内では仮想の算盤(そろばん)が存在しているので、珠の配置や動きをイメージで捉えて計算していて素早く計算することにつながっているようです。普通、計算(筆算)はガチガチの論理的思考~左脳の役割です。ですから懸命に筆算している人に話しかけると「ジャマするな!」と叱られます。しかし、珠算進化形の暗算をしている人は、イメージ処理ですから右脳で計算しています。その結果話しかけられてもその処理は左脳で行いますので、しっかり脳の中で分業し両立できることになります。このように、算盤(そろばん)は使い始めて慣れるまでは電卓と同様に「人間の脳が行っている計算という機能を全面的に置き換える"道具"」ですが、使い熟していくと「人間の脳が行っている計算という機能を"改質"してその性能を高める"道具"」ということになります。すなわち算盤(そろばん)はある意味計算のためと言うよりは「人間成長(進化)促進のための存在」と見なすことが出来そうです。
さて、デジタル(IT)の進化は圧倒的に「電卓」の役割です。省力化・効率化・利便性向上・・・ほとんどが「人間が行っていることを出来るだけ置き換える"道具"」が期待でした。これはこれで大切でしたし、これからも重要でなくなることはあり得ません。しかし、生成AIの出現が大きな契機と言っても良いと思いますが、「人間が行っていることを出来るだけ置き換える"道具"」ではなく「人間を置き換える"道具"」という側面が見え始めてしまいました。ある意味2045年には迎えるとも言われている「シンギュラリティ(技術的特異点)」の始まりなのかもしれません。生成AIに対するさまざまな規制や規則を悩みながら整備する急速な動きは、「シンギュラリティ(技術的特異点)」という人類が初めて経験する事態への戸惑いなのかもしれません。ただ、生成AI(だけに限ったことではありませんが)という技術が出現してしまった以上、人類は共存するしかありません。このときに大切なのが、「人類は生成AIを始めとするデジタル(IT)を、電卓と見なすか 算盤(そろばん)と見なすかの合意が必要である」ということだと思っています。これまでのデジタル(IT)の進化は電卓の位置付けでした。それが求められていました。しかしこの先人間とデジタル(IT)が共存していくことが必要です。しかし、人間とデジタル(IT)は同格ではありません。あくまでも人間が主役なのですから、人間がより成長・進化するようにデジタル(IT)を使い熟すことが求められます。脳内に仮想の算盤(そろばん)が出現して、計算のやり方を改質する役割が(リアルの)算盤(そろばん)であるように、デジタル(IT)も人間の能力や特質を改質する観点で共存する道筋を考えなければならないでしょう。
最近はパソコンやスマホ、スマートウォッチなどで、さまざまな電卓アプリが使えるようになったこともあり、電卓専用機を持つことは少なくなったように感じます。しかしカシオ計算機の関数電卓は年間約2200万台売れ続けています。その大部分は日本ではなく海外です。海外で売れ続けているのは製品そのものの魅力が高いこともありますが、米国、欧州、オーストラリアなどでは中学・高校の授業や米国の大学進学に必要なSAT(大学進学適性試験)を始めとする大学入試で関数電卓を必須ツールとしている背景があります。持ち込める関数電卓の認証制度もあります。すなわち、海外では関数電卓を使うことを前提とした能力を重視しています。その人が持つ"素"の「学識的な能力」と「関数電卓を使い熟す能力」のシナジーが重要だということです。日本では専門的な学科や学校を除き、試験で関数電卓を使うことはまずありません。あくまでも"素"の「学識的な能力」というその人自身が有している能力だけに目が向いています。これはこれで確かに重要かもしれませんが、その人自身が持ち合わせない能力を(関数電卓のような)道具を使いこなして他の人が持ち合わせない能力を出せるのであれば、その方がさまざまな場面で力を発揮出来るはずです。算盤(そろばん)は、脳の使い方に対する柔軟性がある子どもの頃に習うのが効果が高いと言われています。デジタル(IT)も同様でしょう。日本でもGIGAスクール構想が始まりましたが、まだまだ学校教育における『電卓』の位置付けです。『算盤(そろばん)』となるような"シンGIGAスクール構想"がとても大切ですし、すでにさまざまな環境でデジタル(IT)を活用している人たちにも、算盤(そろばん)的なデジタル(IT)リテラシーを高める機会や環境を整備して活用してもらうことが望まれます。
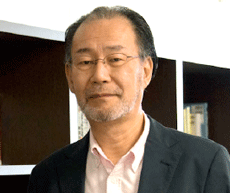
技術士(電気・電子部門)
永倉正洋 技術士事務所 代表
一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事
1980年 日立製作所入社。
システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。
2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。
2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。
2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。
2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。
2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。
2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。
2020年 日立アカデミーを退社。
永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。
お問い合わせ