- 学びたくないけれど、学べてしまう -
2025年2月12日'ひと'とITのコラム
また2月になりました。毎年ひとりで騒いでいる青色申告・確定申告の季節です。今年で5回目の申告なので、さすがに当初ほどの騒ぎ方ではなくなりました。最初は右も左もわからないことで騒いでいましたが、さすがに今は右か左かは分かるようになりました。ただたまに前か後ろか、表か裏かが分からなくなることはあります。
慣れてきた分見落としや思い込みが不安です。特に確定申告の申告書は決まった形式なのですが、実は毎年微妙に変化します。今年は「定額減税の記入」が大きな変更ですが、それ以外にも細かな変更点があり"間違い探し"のノリで騒いでいます。私は会計のソフトを使っているのですが、毎年「今年の申告書対応版」にアップデートする必要があるため、年間使用契約だけでなくサポート契約も必要となります。財務省の都合で毎年変更が生じるわけですが、そこにビジネスチャンスがあるというお役所絡みのフィールドの「あるある」です。
毎年こんなことで騒いでいるのが小さいことと思わせるのが(とは言っても納税は憲法で定められた国民の義務ですから決して小さいことではないのですが・・・)トランプさん絡みのニュースです。
まず書いておきますが・・・トランプさん、あまり好きではありません(個人の感想です!)。言っていること、やっていることが、私の感覚では単なる我が儘で(ドラえもんの)ジャイアンにしか見えません(ジャイアンに失礼かもしれませんが・・・)。 当初はトランプさん絡みの情報には触れないようにしていたのですが、あまりにたくさん降ってくるので飛沫を浴びてしまいました。すると「なんということでしょう!」、彼の言動に興味が湧いてきました。
昨年の大統領選挙、みなさんの記憶にも新しいと思いますが、日本でもキャッチーな言葉が生まれるほどトランプさんへの注目は凄まじかったです。
【【もしトラ】:もしトランプさんが当選したら ⇒【ほぼトラ】:ほぼトランプさんが当選しそうだ ⇒【確トラ】:確実にトランプさんが当選するぞ ⇒【またトラ】:当選しちゃった、またトランプさんだ ⇒【はじトラ】。最後の【はじトラ】は私の造語です。
1月20日の就任で「始まったよ トランプさん」なのですが、気持ち的には「始まっちゃったよ! トランプさん」です。他国の大統領選挙でしかもトランプさんという一人の人間に選挙期間を通じて、キャッチーな言葉を使いながら注目する日本。滑稽ではありますが、注目したのは日本だけではありませんでした。凄いことです。トランプさんが注目を浴びたのは何故か? 1期目の2016年から4年間の在任中の言動、2020年の「奪われた選挙」騒動、その後のバイデン政権の4年間も途切れることがない注目度抜群の言動。この間一貫してさまざまな影響をグローバルに与え続けています。その影響の根底にあるのは「何をしでかすか分からない!」という不安と期待でしょう。要は「トランプさんは分かりにくい!」、「分かりにくい方が注目を集め易い」ということが学べそうです。製品やサービスも適度に分かりにくくした方が注目されて良い結果につながるものもあるのかもしれません。
実は、私はあまり「トランプさんが分かりにくい!」とは思っていません。確かにトランプさんが発出する言動を予測するのは難しいというか不可能なんだと思います。しかし、発出された言動を理解することはあまり難しくない気がします。なぜそう思えるのか? トランプさんの考え方が明確だから。「理念」、「ビジョン」、「行動規範」が分かり易いと言うことです。私の理解でまとめてみます。
「理念」:『Make America great again!(偉大なアメリカを復活させる!)』 は、日本では2016年のトランプさんの選挙スローガンとして有名となりましたが、1980年の大統領選挙でロナルド・レーガン氏が使ったのが最初です。
"again(再び≒復活)"ということは、今は"great(偉大)"ではないが、以前のアメリカは"great(偉大)"だったと言っているわけです。ではいつのことを言っているのか? 恐らくアメリカ国民全員が同じ時代を思い起こしているわけではないでしょう。逆に言うと国民全員が同じ時代を思い起こす必要はなく、「今は最もひどい時代」という印象を植え付けるためのスローガンなのでしょう。アメリカは元々多様性国家なので、日本とは異なり暗黙の共通意識を共有することは出来ないので、明示的な理念を打ち立てなければなりません。だからこのようなスローガンが必要となります。しかもここ数年の「トランプ教」とも言える人々の存在を見ると、かなり効果的であることもわかります。トランプさんが実現しようとしていることは、行政という"サービス業"ですから、そのサービスを「買ってくれる(受け入れてくれる)」国民を増やす「市場創造」が重要となります。この観点でも「理念」と、この後触れる「ビジョン」が大きな役割を担っています。
蛇足ですが、日本でも「理念」を掲げたビジョン経営の重要性が言われて久しいですが、なかなか本物のビジョン経営が根付いていません。しかし、そのわりにはグローバルでもそこそこ戦えているのは、日本の利点でもあり難点でもある「暗黙の共通意識前提の国民性」の存在なのかもしれません。
「ビジョン」:『America First(アメリカ第一主義)』 は他の国から見ればたまったもんではありませんが、もの凄くわかりやすいビジョンです。経営・事業でもビジョンということが言われます。ビジョンはめざす姿を示す言葉ではありますが、日々の事業推進や業務ではさまざまな判断場面で"判断基準"として機能するものです。
例えば「顧客志向」というビジョンを掲げていたら全ての判断場面で「顧客志向≒顧客の満足感」となるように判断しなければなりません。しかし、「顧客志向」を掲げているのにも関わらず、とある判断場面では「利益最大化」で判断してしまうことが結構起きているのも「あるある」なのですが・・・判断基準として機能させるためには誰もが明快に理解できる分かりやすさが大切です。特にアメリカのような多様性国家の運営となると膨大な関与者の存在が前提となるので余計です。
この『America First(アメリカ第一主義)』も、トランプさんのオリジナルではありません。政治的スローガンとしてこの言葉が使われたのは1850年代です。その後、第一次世界大戦期のウィルソン大統領が中立を表明するためにこの言葉を使っていますし、第二次世界大戦へのアメリカの参戦に反対するためのスローガンとしても使われていました。元々は他国での争いにアメリカが参戦しないというナショナリズムの象徴だったようです。しかし戦後のグローバル化を踏まえ、トランプさんが言う『America First(アメリカ第一主義)』は、「国際協調よりもアメリカ優先」というある意味ダイレクトな意味合いとなったように見えます。その分、先ほど触れた国家運営の判断基準として分かり易くなっています。
「行動規範」:『ビジョン達成のためにdealで国家運営を為す』は、さらに具体化して分かりやすさを増大させています。deal、すなわち「国家運営でもビジネスとして行動しなさい」というメッセージです。アメリカの利益が最大になるように取引しながら物事を進める。対外施策の場合は核となる戦術が"関税"。そのために今アメリカにとってのベネフィットにつながっていないと思われるものは一旦やめてdealに持ち込む。さらに、ビジネスなので最大の競争相手を定め、そこに勝つための戦術を立てやすくして効果的に実行する。これらの具現化が、「カナダ、メキシコ、中国を手始めとする関税」、「パリ協定再離脱、WHO脱会」、「対中国施策を有利に進めるためのグリーンランドのアメリカ領土化、パナマ運河のアメリカ移管」・・・
日本から見ると乱暴なものばかりですが、トランプさんの「理念」、「ビジョン」、「行動規範」に則れば、出てきたものの理由は分かりやすいと言えます。
「出てくるものが予測出来なくて、出てきたものも理由が分からない」のはやっかいです。それが問題として認識され始めているのが生成AIでしょう。つまり、トランプさんは生成AIよりはマシだということです。
ところで今回の「トランプ劇場」で凄いと感じたことは、アメリカという国の「急激な変化への高い受忍性」です。トランプさんは1月20日の大統領就任式から1週間で30を超える大統領令に署名しています(蛇足です。日本では大統領令としてひとつに括られていますが、実際は3つの命令形態の総称です)。
この数も凄いのですが、私が一番驚いたのが「前政権によって出された大統領令など78件を取り消す」という大統領令(これは大統領令の括りの中の大統領令)です。この78件のバイデン政権時代の大統領令には人種の公平性実現への支援や、性自認に基づく差別の防止、気候変動への取り組みなどが含まれていて、アメリカ社会の通念を不連続に変えてしまうことをたった一枚の大統領令で行えてしまう! 当然アメリカ国内では反対や懸念の声も多数上がっていますが、大統領が替わることでこのような劇的変化が起こること自体は受け入れているように見えます。
大統領制と議院内閣制の違いはありますが、日本では社会の通念を不連続に変えることは平時である現在ではちょっと考えられません(日本でも過去は、明治維新、太平洋戦争敗戦による不連続な変化はありましたが・・・)。
この「急激な変化に対する高い受忍性」は、所謂イノベーションをたくさん創出できることにもつながっていると感じます。イノベーションという言葉の"定義"もさまざまありますが、『イノベーションのジレンマ』で有名なアメリカの経営学者のクレイトン・クリステンセンによれば、ビジネスの長期的な成功には"破壊的イノベーション"が不可欠であると言っています。この破壊的の意味するところは「不連続であること」が大きな要素です。連続であるということは、今までのものを引きずるわけですから、なかなか革新的な価値にはつながりにくい。だから不連続であることが重要なのですが、この不連続がなかなか難しい。けれどもアメリカ人の「急激な変化に対する高い受忍性」は、この難しい不連続に対する高い受忍性にもつながっていそうです。この辺が日本とアメリカの革新性の違いなのかもしれません。
日本でも「急激な変化への受忍性」を社会全体で高めなければなりません。難しそうですが、実はすでに高まってきているかもしれません。
シチズンが行った「時間に関する意識調査(https://www.citizen.co.jp/research/index.html)」、これ面白いです。この中で社会人1年目の人に「何年ぐらい前を昔と感じるか?」という質問をしています。念頭にあるのは「十年一昔」ですが、その10年との答えが最多でしたが34%、次に多かったのが29.8%で5年、平均年数は6.5年という結果でした。「六年半一昔」ですね。若い世代の方が、時間が速く流れているようです。日本で使われている「和暦」も変化の感覚に影響を及ぼしているとも言われています。なぜならば、和暦だと例えば昭和という64年間を一括りで見がちだからです。確かに昭和元年の1926年から99年間、西暦しかなければ99年間ですが、和暦で見ると昭和(63年間)~平成(30年間)~令和(6年間)という3つの変化で見てしまうことが多いのではないでしょうか。これだけが要因とは思いませんが、日本人の変化に対する感性に影響を与えている可能性は感じられます。
ただ、もし影響を与えているとするならば、これからは一番長い昭和時代を経験していない平成以降に生まれた人たちの時代ですから、「急激な変化への受忍性」が日本でも自ずと高まるのかもしれません。その兆しのひとつが、先ほどのシチズンの調査結果なのでしょう。
今回のコラム、いろいろな話に飛びましたが、これが「トランプさんの言動に興味が湧いてきた」という所以です。トランプさんの打ち出す施策そのものは(腹が立つので)横に置いて、"やり方"やその影響に目を向けると、今回のコラムのようにさまざまな見方を提示してくれます。私がトランプさんを支持していないからこそ冷静に見るとこが出来るのかもしれませんが、トランプさん絡みの情報を"やり方"と"やる内容"に分離しながら付き合っていこうと思っています。
まぁ、結局は私もトランプさんの影響を受けてしまっているということは悔しいですが・・・ (-.-)
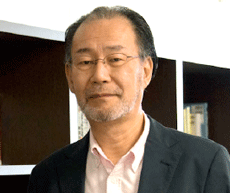
技術士(電気・電子部門)
永倉正洋 技術士事務所 代表
一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事
1980年 日立製作所入社。 システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。
2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。
2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。
2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。
2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。
2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。
2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。
2020年 日立アカデミーを退社。
永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。
お問い合わせ