- 最近の出来事から -
2022年8月5日'ひと'とITのコラム
有ることが当たり前のもの。使用できることを疑わないもの。・・・それらが使えなくなったときに私たちはどのように振舞えばよいか、考えたことはありますか?
今回のテーマは、社会で電話がどのように普及し、今日の携帯電話に至るかを、目の当たりにしてきた筆者ならではお話です。どうぞお楽しみください。
(コラム担当記)
2ヶ月という期間、長いのか短いのか・・・ 何しろ色々なことが起こります。コロナ禍は延々と続いています。すでに第7波に突入し、昨日(7月27日)にはとうとう1週間当たりの新規感染者数が96万9千人超で世界最多となりました。10ヶ月前に感染者数が激減した期間があったことが遠い昔のようです。ちなみに私は7月初旬にワクチン4回目を接種しました。4回ともモデルナ製です。このコラムでも触れてきましたが、今までの3回の接種はいずれも接種したところの筋肉痛と微熱っぽさぐらいの副反応で済みました。今回の4回目は筋肉痛すらほとんど無く、まったく副反応の症状はありませんでした。過去の接種で「生理食塩水を打たれたのではないか」と思ったのですが、今回こそ生理食塩水だったのではないかと思ってしまいます。ま、それでも熱中症予防にはなるかな。(単に鈍感なんだ、という声も聞こえては来ますが・・・)
ロシアのウクライナ侵攻も残念ながら終わりが見えません。戦況の変化もあまり無いように見えますが、これは要注意ですね。 "世界の窓口"としてのマスコミの役割は大きいのですが、5月以降ウクライナの状況に関する報道は影を潜めています。異常な円高、物価の高騰、安倍元首相の銃撃事件・・・色々なことが起きていますから、どうしてもウクライナに関する報道の優先順位が下がるのは仕方ないことです。しかしこのコラムで何回も指摘しているように、多くの人は"報道されない事実"は"存在しない事実"となってしまうので戦況の変化がないとは言えず、知らないだけのことかもしれません。そんな中で、あるテレビ番組は、結構の頻度でウクライナ情勢について伝え続けています。このような番組があると、観る側で選択できます。これが結構大切な気もします。何か大きな事件や事象が起きると、特にワイドショー的な番組は一斉にそれを伝えます。するとどのチャンネルに合わせても同じことしかやっていないので、視聴者が触れる世界がいっぺんに狭くなってしまいます。各局が持ち回り的に、CATVやCS放送の専門チャネル程は徹底しなくても報道の対象を散けさせ、視聴する側が自分の意志を持って選択することで、"存在しない事実"を少なくすることもアリなのかもしれません。ま、視聴率を得るという命題の存在や報道の自由等の柵は多いですが。実はこのようなことはネットの中では可能なのですが、恣意的な情報発信が出来てしまうことがネットの特徴なので、副作用の影響の方が問題となります。この辺にもITリテラシー(ネットリテラシー)を正しく高めないと、せっかくのネットの柔軟な仕組みを活かせないということが見えてきます。
いずれにせよ、この社会は我々が日々受け身として実感する変化の何倍も変化していることは、間違いありません。
最近起きたことで色々考えさせられたのが、KDDIの大規模通信障害です。通信システムの障害は、予測できない要素が絡むのでやっかいです。何が予測できないのか?"トラヒックの渋滞"です。詳しい話はさまざまなサイトなどで為されているので割愛しますが、要はトラブルの原因となった箇所は修理し終わったけれど、そこを通ろうとしているデータが渋滞していてうまく通ることが出来ない、というものです。このデータの発生源は電話利用者の発信です。電話をかけようとしてうまくつながらないとかけ直します。それでもうまくいかないと自分の端末の故障かどうかを確かめたくなって、何回も繰り返し電話をかけることとなります。それでも駄目だと時間を空けてまたかけ直す、それでも駄目だとまた時間を空けて・・・通常なら1個ですむデータ(トラヒック)が数十個、数百個に膨れ上がる、これらのデータがすべて渋滞を長くしてしまう。どの利用者がどのようにかけ直すかは予測出来ません(AI技術などで予測する取組は進んでいます)。さらに最近は、さまざまなシステムと直結しているので、人の介在なくシステムがつながるまで永遠にかけ直すことで、渋滞の列を途方もなく長くさせるということも起きています。ですから今回も途中で「不具合箇所は直ったけれど完全復旧にはまだ時間がかかる」という曖昧にも聞こえる発表がありました。社会を支えるインフラシステムは、復旧させるために予測が難しい・コントロールできない要因にも取り組まなければならない危うさを包含するやっかいな代物だということです(だからこそ通信事業者や通信機器メーカは、日夜技術の進化に、弛まぬ努力を続けています)。
今回の障害でクローズアップされたのが「公衆電話」でした。多くのマスコミが、特に若い人たちが公衆電話を苦労しながら使うシーンを流していました。ネットでも公衆電話の使い方に関する情報が拡散されていたようです。テレホンカードを買って電話ボックスに入ったけれど、テレホンカードがうまく入らなくて四苦八苦しているシーンは印象的でした。受話器を取らないとカードを吸い込まないのですが、最初にカードを入れると思い込んでいるのはなるほどです。かなり前に、ダイヤル式の黒電話が未だに残っている家で、小学生の息子さんの友達がそれを見つけて(遊びがてら)ダイヤルを回そうとしたのですが回せなかった、と聞いたことがあります。電話の発展・進化とともに成長してきた人間にとっては当たり前のことが、初めての人にとっては当然ながら難しく訳がわからない代物なのでしょう。
私の世代は、電話が一般に普及して現在に至るまでをど真ん中で経験してきています。電話が我が家に設置されたのがいつだったかは正確には思い出せないのですが、小学校に入学する前に祖母が亡くなった知らせは電報だったので、1960年頃だったと思います。ダイヤル式の黒電話でした。子供心に「触ってはいけない大切なもの」と感じていたように思います。電話の普及の過程で、『0462-**-****(呼)』と書かれている連絡先が結構ありました。これは「呼び出し電話」と呼ばれていたもので、電話を持っていない人に連絡するときには、近所で電話を持っている家に掛けて呼び出してもらうというものでした。昔、電話は多くの家で玄関先に置かれていました。私の家もそうでしたが、この「呼び出し電話」の仕組みが玄関先に電話を設置する流れを作ったとも言われています。また、特に農村部で使われていたのが「有線電話」と呼ばれていたものです。何軒かの家の電話が同じ電話線につながっていて、誰かが使っているときには使用中のランプがついているので、電話を掛けたいときにはそのランプが消えるのを待ってから使うというものです。いわば何軒かの家が内線電話でつながっているようなものです。電話がかかってくるときは、交換手の「**さん、電話です」という音声が電話についているスピーカーから聞こえるので、受話器を取って話をします。電話線でつながっているので、誰かが使っているときに受話器を耳に当てると全部聞こえてしまいます(話しかけると相手にも聞こえてしまいます)。今の時代には考えられませんが、先ほどの呼び出し電話も含め、プライバシーや互いの信頼関係などが、今の時代とはかなり異なっていたことを感じます。
電話が生活に浸透すると、家にいるとき以外にも使いたくなるのは当然です。公衆電話が拡がっていきます。私が知る最初の公衆電話は赤電話でした。使える硬貨は10円玉だけです。赤電話の前は青電話が存在したようですが、これは10円玉を入れて掛けたときに、相手が話し中であっても硬貨が戻らないということで不評だったようです。ピンク電話もありました。これは、個人電話と公衆電話を兼ねたもので、公衆電話が通信事業者(当時は電電公社)が設置していたのに対し、ピンク電話はその電話の所有者が公衆電話的に使えるようにしたものです。どんなところで使われたかというと、喫茶店やレストランなどに多くありました。私が大学生の時には部室に設置していました。地方出身の部員は自宅に電話がないのが当たり前でしたから、部室でゆっくり使えることは大いに助かったようです。公衆電話が整備されると「発信する」ことは、現在の携帯電話ほどの場所の自由さではありませんが、自宅という場所の制約から解放されました。逆に「受信する」すなわちかかってくる方はそもそも"あり得ない"と思い込んでいたので、多くの人はニーズにもならなかったと思います。ただ、さきほどのピンク電話は個人電話ですから、例えば喫茶店の連絡先として公開されていましたから、「受信する」必要があるときはその喫茶店を連絡先としての拠点として行動していました。今考えると結構電話の設置場所を、自分の行動の要素として知らずうちに組み込んでいたのだと思います。ところで、現在の公衆電話もそうですが、公衆電話に電話を掛けることができるということをご存じでしたか?実は公衆電話も電話端末ですから、電話番号が振られています。その番号に掛ければ公衆電話も鳴動します。ただ、公衆電話の電話番号が基本的に公開されていないので掛けられないだけです。これはたまに映画やドラマ、小説で使われています。よくあるシーンは身代金の受け渡しで、まず「公衆電話のところに金を持って行け」、そこに金を持っていくとしばらくして公衆電話が鳴動します。すると金を持っていった人はびっくりし、恐る恐る電話に出ます。すると「次は何時までに*****に行け」というような指示を受ける、というものです。こういう特殊なシーンは別としても、公衆電話の電話番号を公開して、そこに掛けるとスピーカーモードとなって「**さん、近くにいたら出てください!」と呼びかけるものがあったら面白かったと思います。
電話の普及は多くの生活シーンを便利にしてくれました。便利さの多くは"時間の短縮"が起点にありました。例えば友人と大森で会う場面、電話が当たり前に使える前は ①頻繁にあっている友人の場合は別れる時に「では来週の火曜日の14時に大森駅北口で」、②ずっと会っていない友人の場合は手紙で「拝啓 ~ では、7月29日(金)の14時に大森駅北口でお待ちします。 敬具」のどちらかになります。敢えて挙げれば③「カネナクメシクエナイ オゴッテクレ アシタ14ジ オオモリエキキタ」 という電報もありました(この文字数では高くつきますが・・・)。③はイレギュラーなので無視するとして、①②とも電話が使える場合と大きく異なるのは何だと思いますか?両方とも会うことを決めてからの時間が長いということです。①は別れてから7月29日の14時までは連絡の取りようがありません、②は手紙を出してから(もしくは先方からの承諾の手紙を受け取ってから)7月29日の14時まで連絡できません。その間に突発的に会えない、もしくは日時を変えたいことが起こっても対処が難しいということです。要するに柔軟性が無いということで不便ですよね。でも、この時代多くの人は不便とは思っていません。これが当たり前のことです。"予定"というものに重みがありました。ここに電話が登場します。電話であればいつでも会う日時を決められます。変更も可能です。柔軟性を手に入れることが出来ました。便利です。時間の制約が格段に少なくなりました。しかし、この柔軟性も会うために家を出るまでが対象です。家を出てしまえば連絡手段がないことは、電話が有ろうと無かろうと変わりません。大森駅に行く間に突発的な事象が起こることは当然ありました。よくあるのが電車の遅れ、だから待ち合わせを駅にするのも工夫でした。電車の遅れだったら駅でアナンスしてくれるので、時間に遅れることを間接的に伝えてもらえるということです。それでも"待ちぼうけ"は頻繁に起きました。でも今と比べ"待ちぼうけ"を食らうことに対して寛容でした。だって仕方ないことです。お互い様です。とはいえ出来ればそうなりたくないので、待ち合わせを先述の連絡がつく喫茶店や、店内放送で知らせてくれるデパートなどにする、伝言が出来るように駅に「伝言板」が設置されているなどの工夫がありました。
さて、携帯電話の出現です。携帯電話の便利さは、便利という実感に止まらず日常の行動様式まで変えました。携帯電話(メールやSMSも含め)があれば、極端な話事前に予定しなくても会うことが出来ます。「これから大森で会わない?」これで通じます。何時に大森のどこで を決める必要はありません。電車が遅れても、途中で忘れ物して引き返しても、途中で徘徊してもすぐに相手に伝えることが出来ます。前は、電車が遅れると相手を待たせてしまうので早めに家を出ることも多々ありました。結果電車が遅れずに到着すると当然時間が余るので、当時は駅の近くで本屋など時間を潰せるところをよく探したものです。今はそんな必要はありません。携帯電話の有無で、人生の限られた時間の無駄が激減したとも言えるでしょう(ただ、時間を潰すというある意味贅沢を失ってしまったとも思えます)。そして、行動様式のほとんどが携帯電話を使える前提に変わり、定着し、当たり前となりました。ま、これが技術の恩恵を受けるということなのですが・・・
ここに大規模な通信障害起きました。新しい生活様式の基盤を直撃しました。今日(7月28日)に提示されたKDDIの報告書によると、個人契約だけではありませんが約3000万回線に影響があったようです。通信障害はご存じのように今回のKDDIだけではありません。2018年にソフトバンクで約3060万件、2021年にドコモで音声回線:460万人、データ通信:830万人が影響を受ける障害が発生しています。しかもやっかいなのは通信障害という通信そのものものだけでなく、通信を基盤として使っているシステムなどがあまりにも多いことです。私もKDDI利用者なので今回「これも携帯電話がないと駄目なのかぁ」と改めて認識させられたことも多かったです。例えば最近のセキュリティ強化のための2段階認証。ほとんどが携帯電話を使っています。これが使えないことで、いくつかの手続きが出来なくなりました。また、自動車の緊急時通報システムが使えなくなりました。幸いこのシステムを使わなければならない事態は起きなかったのですが、このシステムがKDDI回線を使っていることを初めて認識しました。2016年に第22回コラム『スマホ断ちの日 "スマホを使わなかった日"の日記』で、1日スマホを使わないで過ごして色々な気づきがあったことを書きました。この時は自分で決めたので、「使わない」でした。気持ちにゆとりがありました。今回は「使えない」でしたから気持ちにゆとりはありません。人は不意打ちに弱いことも痛感しました。
「形あるものは壊れる」の格言ではありませんが、システムである以上、残念ながら障害はゼロにはなりません。しかし障害をゼロにする努力は出来ます。さらに通信が使えなくなったときにその影響を小さくする努力も出来ます。これは前提として受け入れるしかありません。
障害をゼロにする努力は、基本的には通信事業者の範疇です。利用者側で出来ることは、障害をゼロにするにもコストがかかりますから、適正な使用料をきちんと払うことぐらいでしょうか。通信が使えないときの影響を小さくする部分は、通信を利用している側も積極的に取り組む必要がある部分です。通信を使っている事業者の範疇と最終の利用者の範疇それぞれで考えなければなりません。最終の利用者は、通信そのもの利用者と、通信を利用しているさまざまなサービス等の利用者の両側面があります。さまざまなサービスの範疇は、日頃からそのサービスがどのような通信基盤を使っているのかを知っていることも重要となります。今回も一部地銀で発生したATMが使えなくなる事象のように、なぜ通信とは関係ないと思われるサービスが利用できなくなったのか戸惑った人も多かったのではないでしょうか。契約等のハードルはあるかもしれませんが、サービス利用者も知るべき事を利用開始時から開示してもらうだけで、不安感の軽減につながると思います。さらに代替手段を準備してもらうのも助かります。先ほど触れた2段階認証。事業者によってはコード発信の対象を携帯電話かPCメールかを選択できるようにしてくれているものもあります。助かります。
通信の利用者としては、携帯電話がなかった時代を参考とした対処を、日頃から考えておくことも必要なのでしょう。先述の「これから大森で会わない?」だけではなく、「じゃぁ30分後に大森駅の北口改札で」まで会話をしておけば、そのあと通信障害が起きても最低限会うことは出来ます。便利さの陰で我々は行動様式を変えてきています。それが"便利"ということなのですが、変えられると思う変化をすべて取り込むのではなく、"便利の素"が使えなくなった場面を想像して、敢えて変えない部分を残すことが必要なのではないでしょうか。
こういうことは「喉元過ぎれば熱さを忘れる」になりがちです。第15回のコラム(2015年) 『ITはホモサピエンス進化の環境を作り出しているのか?』の結びで『災害対策訓練のように年1回で構わないので、「人間の本質を思い出す日」としてスマホなどITを使わない日(使えない日)を制定するなど、ホモサピエンスの種の進化という大き過ぎるぐらいの視点からも「ITとどう付き合っていくべきなのか」という方策を考えなければならないのではないでしょうか? 人類が生み出した自然現象ではないITという技術をホモサピエンス進化のための基盤とするために。』と書きました。この時はITが浸透しても「人間の本質を思い出す日」として「ITを使わない日」の制定を提示したのですが、あらためて「人間の本質を思い出す日」+「ITを失った時に生き延びるため」として「ITを使わない日」を提唱したいと思います。
先日、MicrosoftのTeamsに障害が発生して一部使えなくなりました。特にリモート環境が基盤化している昨今ですから影響も大きかったのですが、世界中の多くの利用者からは、「ゆっくり直してくれ!」という声が寄せられたそうです。ICTが仕事の基盤となった時代だからこその "仕事が出来ない理由"を、新たに手に入れる事が出来たということです。
結局・・・餃子+イチゴジャムは諸般の事情により試すことが出来ていません。しかし、教えた友人からは「いける!」と一言メールをもらいました・・・
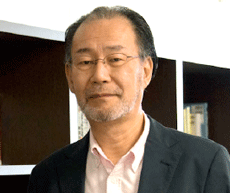
技術士(電気・電子部門)
永倉正洋 技術士事務所 代表
一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事
1980年 日立製作所入社。
システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。
2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。
2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。
2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。
2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。
2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。
2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。
2020年 日立アカデミーを退社。
永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。
お問い合わせ