- 「善悪」と「損得」 -
2023年10月6日'ひと'とITのコラム
'ひと'とITのコラム 第53回に続き、ITリテラシーと日本人気質の関係性をテーマとしてお送りする第2弾です。
多様性の社会。時代とともに変化する社会においても、「善悪」の判断と「損得」の考え方には、国民性による影響がどれほどあるのでしょうか。人々の価値観や行動は、時代とともにどう変化しているでしょうか。
筆者がかつて経験したいくつかの事例から考察します。
(コラム担当記)
前回 第53回コラムでは「マイナンバーカードを巡る"騒ぎ"に見え隠れする日本という国の深層」というテーマで、「完璧さの追求」と「受け身の姿勢」の観点から日本人気質について触れました。このうち「完璧さの追求」について、有り難いことに読んでいただいた方からメールをいただきました。ご指摘は「完璧さを求めることは自然なことではないか」というものです。このご指摘はその通りです。完璧であることに超したことはありません。ただ言葉足らずだったので、私が伝えたかったことがうまく伝わらなかったと反省しています。伝えたかったことに気付いた私の経験を紹介します。今から25年ほど前の話です。会社でもパソコンの導入が始まった頃です。今のように一人一台の環境とはほど遠く、職場で数台といった感じです。当時私が担当していた某電力会社から、「原子力発電所の中央制御室にパソコンを導入したい」との相談が、日立と某外資系企業にありました。普通だったら見積価格勝負の"競争引き合い"になります。要は「安い方を買う」という当たり前のことなのですが、私にとっては大問題でした。現在のパソコンはメーカが異なっても多くの部品などが共有化されているので、コストの大きな違いは無いといっても過言ではありません。しかし当時のパソコンは、各社が独自に開発をしている状況でしたので、コスト≒価格に大きな隔たりがあることもありました。特にパソコンですので沢山販売している方が安く提供できるのは当たり前です。当時日立も頑張ってはいましたが、相手は外資系です。すでに多くのパソコンの導入が進んでいた欧米を中心に多くのパソコンを売ってきています。当然ながら価格勝負では勝ち目がありません。案の定、価格提示してみると、外資系企業の方が1台当たり2万円程度安い結果となりました。この電力会社は、コンピュータ導入開始時から日立を選んでいただいてきたので、電力会社としても出来れば日立製を導入したいとのご意向もあり、色々相談にも乗っていただきました。そんな中で、ひとつ着目したのが"品質"でした。価格の差はさきほど触れた"販売台数"の要素は大きいのですが、もうひとつの要素が"提供品質"の違いです。当時日立のパソコン開発を担っていたのは、所謂汎用コンピュータを開発・製造している工場でした。また、時代背景的に「なかなか壊れない製品は良い」という根強い風潮のもと、「日立の製品は故障が少ない」というブランドイメージもさまざまな観点で評価されていました。当時はパソコンを含め製品の品質の良さは「壊れにくい」が代表格です。原子力発電所の中央制御室で使うパソコンですから、この「壊れにくい」は絶対的なアドバンテージになるはずでした。ある日、パソコンの設計担当者にも足を運んでもらい、「壊れにくいパソコンを実現するために、日立はパソコンに使用する部品を全数チェックしていて手間かけているだから価格も高くなるけれど、それ以上の価値があります。」と説明してもらいました。この時のお客さまの反応は「なるほど、日立のパソコンの品質が価格に見合っていることは良く理解しました」でした。「おっ! これはいけるかな!」という言葉が頭をかすめました。しかしお客さまから発せられた次の台詞が衝撃的でした。「パソコンは汎用コンピュータとは違って、ある程度のところで壊れて欲しいんだよね!」・・・「はぁー!?」てなもんです。今までお客さまから「壊れないよね!」は毎回念押しされていましたが「壊れて欲しい」は初めて聞く台詞です。なぜ壊れて欲しいのか。お客さまから「新しいOSが出るとそれを使いたいのだけれど、古いパソコンでは性能が足りなくなってスムーズに動かないよね。会社で買うと壊れない限り、性能が良い新しいパソコンに変えられないんだよね。だから5年ぐらいで壊れてくれるとちょうど良いんだ」。当時のITは、まだまだハード的な性能が発展途上で、処理が複雑になると性能が追いつかないことがままありました。当時パソコンのOSであるWindowsも毎年のように更新され、さまざまな機能などが追加されていました。特に数年で大きな更新があり、それまでのパソコンのハード性能では使いにくくなることが頻発していました。目からうろこでした。「壊れにくい」という品質は絶対的な価値だと思い込んでいましたが、実は「品質も仕様である」と気付かされました。「品質が高ければ若干高くても仕方がない」という時代もありましたが、ある程度の品質の製品が提供されるようになると、品質の高さは必ずしも価値ではなく、値段に見合った品質が求められる、ということです。「完璧さ」は究極の姿です。しかしコストも掛かります。"費用対効果"の効果に見合った品質をしっかり組み込んで考えることが大切です。完璧さを求めることは自然ですが、当たり前ではないことを認識すること、すなわち前回書いた『高品質は当たり前ではなく、時間とコストがかかるスペックの一つ』であり、さまざまな要素のひとつとしてバランスさせるという感覚の共有が求められます。
ちょっと余談です。「出来るだけ長く使えることより、使えなくなるタイミングがわかる品質」は結構ニーズがありそうです。例えばホテルや式場などで結構大変なのが電球の管理です。こういう場所では電球が点かなくなってから取り替えるのではなく、点かなくなる前に替えることが求められます。だからといって、まだまだ寿命が長く残っているのに替えてしまえば無駄なコストがかかります。この管理をどのように行っていたのか?基本的には熟練者の長年の勘でした。今はLED化しているのでかなりやりやすくなっているとは思いますが、LEDもやはり取り替え時期はあります。この大変さはどこからきているかというと、電球の寿命がばらついていて当たり外れも多く、球切れしてみなければ正確なところが分からない点にあります。ならばいつ球切れを起こすかがわかれば解決です。すなわち、出来るだけ長く電球が保つように品質を考えているからばらつくわけですから、出来るだけ長く使えるという品質を高めるのではなく、いつ球切れを起こすかを仕様として設定してその通りに球切れするとすれば、熟練者の勘に頼らなくても済み、メンテナンスコストも抑えられます。"壊れる製品が壊れるべきタイミングできちんと壊れる品質"は色々役立ちそうです。
さて、別の日本人気質について触れたいと思います。
私が30歳代前半(今からおよそ35年前)に、電力会社の方々とIT(コンピュータ)システムの動向調査で、欧米の電力会社の視察に行きました。このときドイツの某電力会社とのフリーディスカッションの場で、"電力料金不払いの利用者に対する対応"について話題となりました。日本では督促状などを発行した後、不払い者に対し集金人が何遍も訪問して説得している旨説明しました。日本で暮らしていれば恐らく当たり前のプロセスに見えると思います。しかし、このときドイツの電力会社の方々から「なぜ、そんな無駄なことをしているのか?」と驚きの声があがりました。何が無駄なのか? 「集金人はそれなりの人数がいて、それなりの人件費がかかっているのだろう?不払い料金の回収金額はその人件費等のコストを上回るのか?」 確かに不払い料金を全額回収出来たとしても赤字です。

さらにもうひとつ・・・特にヨーロッパで電車を利用したことがある方はご存じかと思いますが、多くの駅で日本では当たり前の改札機(ラッチ)を見かけません。ラッチレス(ラッチ=改札機、改札機がない駅)となっています。私が利用した25年ほど前、ドイツのフランクフルト空港駅でもラッチレスでしたし、フランスの国鉄の駅のほとんどもそうでした。日本でも地方の乗降客が少ない駅では無人(改札は車掌か運転手が兼ねている)というところもありますが、ドイツではフランクフルト空港駅を始めとして大きな駅でもラッチレスというところが多くありました。フランクフルト空港駅には券売機はあります。購入した乗車券は、ホームに行く途中にある打刻機に自分で差し込んでスタンプを押す必要があり、これが改札に相当します。しかしラッチ(改札機)は一切ありません。降車駅にもラッチ(改札機)もなく、乗車券の回収もありません。乗車券を買わなくても簡単に電車に乗れてしまうということです(ロンドンの地下鉄や欧州の国際列車などはしっかりとした改札ゲートが存在します)。つまり無賃乗車をしようと思えば簡単に出来てしまいます。では無賃乗車を野放しにしているか というと、不定期に車内検札は行われています。この時に乗車券を持っていなかったり、持っていても先ほどの打刻をしていないと無賃乗車と見なされ、高額の罰金を払う羽目となります。無賃乗車の抑止策はこれくらいです。確実性を高めるためには、日本で当たり前である全駅でのラッチ(改札機)設置ですが、これには多額のコストが掛かります(Suica導入時の開発費の約7割が改札機絡みだったと記憶しています)。このコストをかけて得られる無賃乗車の回収金は、コストを上回ることは決してありません。しかし、日本はこのコストをかけている国です。
これら二つの話、共通しているのは『料金不払いの人を減らすためのコストと、それによる回収金のバランスが取れるのか?』ということです。基本的には収支は成り立ちません。ではなぜ日本では収支抜きでも行っているのか? 電力会社、鉄道会社にお訊きしたところ共通して出てきたのは、「しっかり利用者全員に適切な料金を払ってもらう取り組みを行っていることが大切」ということです。これは電気を使ったにもかかわらず使用料金を払わない利用者、無賃で乗車する利用者を極力減らすという観点もありますが、ここの部分は先ほど書いたように"全額回収"をめざすことに相当しますので、これだけでは赤字です。では、主目的は何か? 利用者全員に払ってもらう取り組みをしていないと、"支払っていない人"がいることを知った"支払っている人"が「ならば私も払わない」というマインドに走ってしまうので、それを抑えたいということだそうです。すると今度は先のドイツやフランスなどの他の国では必要ないのか?という疑問が湧いてきます。先ほどのドイツの電力会社でのフリーディスカッションでも話題となりました。ここで日本とドイツのある違いが見えてきました。
ドイツの方々の話では、ドイツでも電力料金を払っていない利用者がいると、その周辺で「払っていない人がいるのに何で私から料金を取るのか!」と言う利用者もいるけれど、多くの利用者の思いは「不払いの人はかわいそうな人」というニュアンスなんだそうです。この「かわいそう」というのは、「神様の教えを守れないかわいそうな人」ということです。すなわち、ベースに宗教の教えがあり、それに背いている人が不払いの利用者ということです。ですから、そういう人が近くにいても、それを真似しようとは思わないわけです。自分も料金を払わないかどうかという"判断"ではなく、神様の教えを守るかどうかという"判断"なのです。換言すれば他人がどうであれ自分の「善悪」の判断が優先されるということです。当時私はこの話を聞いたときに目からうろこでした。日本で育つと、さまざまな"事象"を判断するときに、宗教的要素を前提とすることはほとんど無いと言っても過言ではないでしょう。特に日常生活で意識することはまずありませんでした。
では、日本ではどうなのか? 電力会社の方曰く『"支払っていない人"がいることを知った"支払っている人"が「ならば私も払わない」というマインドに走ってしまう』のマインドは多くの場合、「善悪」ではなく「損得」が前提となっているそうです。不払いの人は得していて、きちんと払っている自分は損をしているというマインドです。「損得」は比較(相対)で認識されるので、このマインドも理解は出来ます。ただ、多くの人は「きちんと支払って損している気分だけれど、払わなければならないよね」という「善悪」に落ちつきます。ただし、ドイツの例のような宗教的根源と比べると脆さを感じます。不払いの人が少ない場合はあまり靡く人は多くないのですが、不払いの人が増えてくると雪だるま式に「不満⇒不払い」という流れが加速するようです。従って、少しでも不払いの人を減らすことと、不払いの人を一掃するために最大限の取り組みをしていることを示すことが重要となってきます。この「損得」がまず頭に浮かぶというのはさまざまな場面で確かにあります。自分もそうですが、テレビでよく放映される警察もののドキュメンタリー番組などでよくあるのが、自動車を運転中にスピード違反などで捕まった時です。まず頭に浮かぶ文言は「しまった!」、次に浮かぶのが「言い逃れ出来る言い訳があるか?」、その次に「他にも自分よりスピードを出している車があるのになんで自分だけが捕まるのか?」、この辺で警官がやってきて「お急ぎでしたか? ちょっと速いようなのでお停めしました」とくるわけです。すると口から出てくるのは「なんで私だけなんですか!?」・・・これすでに「善悪」からは遠く離れた世界に入り込んでいます。スピード違反という「悪」の領域の中で、他にもスピード違反している車があるではないか! という「損得」で考えてしまっています。「善悪」がベースであるならば、他の人がどうであれ自分はスピード違反という「悪」をしてしまった、ということになるはずです。このマインド、日本だけのものかは分かりませんが、宗教的な拠り所を持ちにくいことから日本人気質を構成する大きな要素なのではないでしょうか。断言は出来ませんが、コロナ禍でのマスク着用で話題となった「日本は同調圧力が強い」というのも、この「善悪」よりも「損得」というマインドに連なる気もします。「善悪」は絶対的な要素として「善」「悪」が存在しますが、先にも触れたように「損得」は相対的な要素として「損」と「得」が存在します。日本は結構昔から「平等意識」が高かったように思います。江戸時代「士農工商」という身分制度で格差文化が前提と思われていましたが、最近の歴史評価は変わっています。そもそも江戸時代には「士農工商」という言葉も存在していなかったようです。「「士農工商」という身分制度が江戸時代に存在していた」と言い始めたのは明治政府です。明治維新直後「江戸時代は「士農工商」というとんでもない制度があったが、明治政府はこれを無くして平等な民主的社会を実現した」ことを強調して、民意を引き寄せるために使い始めたことがわかっています。蛇足ついでに加えると、江戸時代の農民の生活、みなさんはどのような印象でしょうか?毎年 年貢に追い立てられて、自分たちは自ら作った米を食べられず、ひもじい生活を送っていた、てな感じの方も多いのではないでしょうか。これ、時代劇の影響です。実は、江戸時代の農民は結構豊かな生活を送っていたことが分かってきています。1697年に出された「百姓身持之覚書」で、農民に対して「質素倹約に努めるべし」との戒めが書かれていました。また江戸時代の農業生産力は現在とほぼ変わらないことが幕末期に出版されている農書からわかっています。当時の人口は約3300万人、現在の約1/4で、約8割が農民です。現在と同等の収穫量の米をいくら年貢で収めたとしても、農民が米にありつけなかったはずがありません。歴史の教科書はかなり変わってきています。たまに興味を持って歴史の最新情報を仕入れないと、子どもに笑われてしまいます。閑話休題、日本は「平等意識」が高く、結果「常識の共有」も深かったことで、一体感も生まれる素晴らしい文化を持っていたように思います。この「平等意識」のもとでは「損得」の感情は芽生えにくい、確かに私が子どもの頃は今ほど「損得」が表面化する状況ではなかったように思います。しかし豊かな社会の形成で、生活者の意識やライフスタイル、働き方などが多様化し、昔ながらの「平等」が崩れてきています。生活のさまざまなシーンで、具体的な「格差」が表出してきています。いわゆる「格差社会と」呼ばれているものです。この「格差社会」という文言の裏には、全てのシーンではありませんが「ズルい!」的な「損得」の感情が潜んでいるようにも感じてしまいます。20年ほど前にヨーロッパの某有名ブランドの日本の店舗に就職した人から聞いた話ですが、日本は特殊な市場で、「若い人が一生懸命アルバイトでお金を貯めて買いに来る」、この光景は日本だけなんだそうです。特に欧米で有名ブランド品を購入する客層は高所得者層に限られていて、普通(?)の消費者は来ないそうです。このため某高級ブランド会社では、日本の販売員に「特に若いお客さまに販売するのは2商品/回までにするように」との指導があったそうです。一つひとつの商品をじっくり味わってもらいたいという思いと、無理して購入して金銭トラブルに巻き込まれたりすることを未然に防ぎたいという思いからの方針のようです。このように、日本の「平等意識」とは異なり、欧米はもともと「格差」があるのが当たり前です。だから「損得」の感情は、先述の宗教観的「善悪」の存在もあって芽生えにくいのでしょう。「損得」ではなくあくまでも「相違」です。しかし、日本で「格差」が身近になったのは最近のことなので、「同調圧力」の存在が一端を示しているようにマインドの部分はまだまだ「平等意識」から離れ切れていません。「平等意識」のスタンスで「格差」に触れると、「相違」ではなく「損得」になりやすいのは容易に想像できます。
前回と今回のコラムで触れた「完璧さの追求」、「受け身の姿勢」、「平等意識のもとの損得感情」という日本人気質。 決して悪者にしようとしているわけではありません。これらが素晴らしい日本文化の形成や、日本の強みに繋がってきたのは確かです。ただ、時代とともに社会は変化してきています。その変化は日常生活などの具体的な事象面と意識面双方で起きています。この両面が同期して変化してくれれば良いのですが、事象面が先行して意識面が後を追うのが普通です。この過渡期の不安定さが、いままでにはない感情を生み出している気もします。これら過渡期の複雑さをさまざまなシステムやビジネスモデルですべてに対応しようとすると、膨大なコストがかかることになります。この複雑さを社会全体で共有し、一人ひとりが理解・納得する努力も求められているのではないでしょうか。
※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※Windowsは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
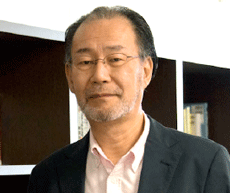
技術士(電気・電子部門)
永倉正洋 技術士事務所 代表
一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事
1980年 日立製作所入社。
システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。
2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。
2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。
2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。
2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。
2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。
2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。
2020年 日立アカデミーを退社。
永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。
お問い合わせ