- 人間が持つ根本的なバイアス要素 -
2022年10月5日'ひと'とITのコラム
「人はなぜ吟味しないと情報を正しく把握・理解できないのか? 人は何かしら"ベースとしてのバイアス要素"を持っているのではないか?」(以上、第48回コラムより引用)という筆者が長い間感じてきた問いに対し、筆者が見つけた答えは何なのか。
さあ、皆さんもいっしょに人類の歴史をたどり、想像してみましょう。
(コラム担当記)
最近のコラムの出だしは「時間の流れが速いのか遅いのか、わからなくなっている」というものが多くなっていますが、この2ヶ月も密度が濃かったように感じます。昨日(9月24日)でちょうど7ヶ月経ったロシアのウクライナ侵攻、ウクライナの反攻が報じられています。イギリスのエリザベス女王の逝去と国葬、コロナの第7波の予測し難かった収束傾向、台風の巨大化・猛烈化など亜熱帯日本への着実な変化、風呂場のリフォーム(?)・・・色々起きました。時間経過が早いのか遅いのかの感じ方は人によって異なりますが、激動であることは間違いないでしょう。
半導体不足による品不足も家電市場や温水湯沸かし器、自動車など色々なところで解消されていないようです。そんな中で、大手家電量販店が家電のリユース製品の販売に力を入れている、という報道がありました。2年間の保証付きで新品の半値だそうです。自動車なども中古市場が活況を呈しているとのこと。リフォーム業者に聞いたところ、温水湯沸かし器が壊れた場合はすぐには対処できない状況なので、大切に使って欲しいと言われてしまいました。結果として今回の半導体不足は、リユース市場の活性化や大切に使う意識の醸成など、図らずもSDGsの実践を促すことにつながっています。
さてこのコラムでは情報のバイアスについて頻繁に触れてきました。最初に注目したのは2019年10月30日に掲載した『第35回 写像? 虚像? - 我々は、「歪んだ写像」で事実を認識できているのか -』です。このコラムで『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』(ハンス・ロスリング他著、日経BP社発行 ISBN978-4-8222-8960-7)を紹介し、我々の多くが情報にバイアスがかかっていることを述べました。ちょっと長くなりますが、この時の文面を引用してみます。 『この本では冒頭に質問がいくつか並んでいます。 著者がいろいろな講演会などでこれらの質問を出すのです。 例えば「世界中の1歳児の中で、なんらかの病気に対して予防接種を受けている子供はどのくらいいるでしょうか?」、回答は3択で「A 20% B 50% C 80% 」、現代のグローバル社会の状況を問うものが並んでいます。 講演に参加している人は医者や施政者、科学者など高度な知見を持っている人がほとんどなのですが、毎回10%以下の正答率だったそうです。この夏から私もある研修でこの質問を使っています。 8問程出すのですが、今まで約250人でやはり10%以下の正答率です。 特に先ほどの例で採り上げた質問は、今のところ正答者は1人です。 著者曰く『3択なのですからチンパンジーでも33.3%の正解は出せます』と。 確かにそうですね(250頭(敢えて"匹"ではなく)のチンパンジーならば83頭正解が出せるということです)。 なぜこうなってしまうのか?先ほど書いた「フィルター」もしくは「バイアス」の影響が大きいということに帰結します。 チンパンジーより多く情報に触れる機会が多い人ほど正答率が低いことからも、情報過多の時代の特徴が浮かび上がってきます。』
この時から約3年経ちました。8問の質問を研修で使い続けていますが、やはり正答率は10%を超えることはありません。予防接種の質問の正解者は1名から増加はしましたが・・・ 3年前はこのフィルターがかかる要因として、 『私が子どもの頃は、報道される範囲や密度、頻度も少なかったですし、インターネットのような情報取得手段もありませんでした。 従って、感覚的に実際の世界で起きていることは「知らない」がデフォルトです。知らないことが前提です。 そうなると限られた「知ったこと」は「正しく」知ることが出来ていたのかもしれません。 特に知るためには努力が必要でしたから、情報の吟味を汗かきながら行っていました。 情報を見る目が養われていたといえるでしょう。 要するに、人間は楽して情報を手に入れられると鵜呑みにしてしまう怠惰な動物なんだということを、特に今の時代は認識することが大切なのでしょう。』 という仮説を提示しました。情報が手軽に入手できることが、その情報を吟味する機会を失わせているということです。このことはその後何回か触れている、情報との付き合い方の難しさやプロパガンダ、フェイクニュース(情報)が巷に溢れる温床でもあります。では、人はなぜ吟味しないと情報を正しく把握・理解できないのか? 人は何かしら"ベースとしてのバイアス要素"を持っているのではないか? 実はずっと気になっていたことです。最近読んだ本の中にその答えらしきものを見つけました。
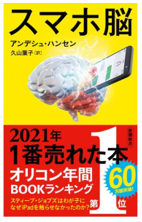
『スマホ脳』(アンデシュ・ハンセン著、新潮新書 ISBN978-4-10-610882-1)、2020年に発刊され話題となった本です。読まれた方も多いのではないでしょうか。アンデシュ・ハンセンは、前作の「一流の頭脳」がスウェーデンでベストセラーとなり人気を得たスウェーデン出身の精神科医です。ちなみに『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』の著者のハンス・ロスリングもスウェーデン出身の医師で、スウェーデンの研究や発信は注目株です。『スマホ脳』で何を見つけたのか?一旦先ほどの『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』の「ワクチンに関する質問」に話を戻します。
「世界中の1歳児の中で、なんらかの病気に対して予防接種を受けている子供はどのくらいいるでしょうか?」、答えはCの 80%です。みなさんのイメージと合いますか?研修ではAの20%に手を挙げる人が最も多く、次は僅差でBの50%です。3択の場合、正解がわからなくて何の確信もないと真ん中を選ぶ人が多くなるのですが、この設問ではAの20%がいつも多くなります。恐らく正解はわからないけれど「ワクチンを接種している1歳児は半分も居ないとはず」という"間違った確信"を持っている人が多いのだと思います。この"間違った確信"はどこから来ているのか。みなさんは1歳児のワクチン接種状況に関する情報を、どのようにして入手してきましたか?「自分で興味や意識を持って調べた情報」という人は希でしょう。多くの人は恐らくマスコミのニュースなのではないでしょうか。ではどういうニュースなのか?「最近アフリカの複数の国でコレラが蔓延し、特に小さな子供が多く亡くなっています。これは特に小さな子供へのワクチン接種が拡がっていないことが大きな要因と考えられます。」 このようなネガティブトーンのニュースがほとんどではないでしょうか。「最近世界中で小さな子供へのワクチン接種率が上がり、約80%の1歳児が接種し終えました。」といったポジティブトーンの話題は、なかなかニュースとして取り上げられません。取り上げられるとすれば、例えば貧困国でのワクチン接種に多大な貢献をした組織や人が、ノーベル賞は無理としても何か受賞をしたような場合でしょう。ただしワクチン接種率はメインではなく、あくまでも"貢献に対する受賞"を補う位置付けです。すなわち、日常我々が触れるマスコミのニュースは、 "良いニュース"よりも"悪いニュース"の方が圧倒的に多いということです。何故なのか?話は簡単です。"悪いニュース"の方が視聴する人が増えるからです。放送する側も"悪いニュース"を選択したがるからです。ではそれは何故なのか?ニュースを視聴する側の人間も、ニュースを提供する側の人間も、"良いニュース"よりも"悪いニュース"の方に興味があるからです。ということは人間は単に"悪いニュース" が好きな動物であるということなのでしょうか?この疑問が、先ほど書いた「人は何かしら"ベースとしてのバイアス要素"を持っているのではないか?」と気になっていたことです。
『スマホ脳』が示唆した答えらしきものとは・・・「人間は現代社会に適応するようには進化していない」ということです。東アフリカに我々の種が出現したのは約20万年前です。人類の歴史を大雑把に俯瞰すると次のようになります。
人類の歴史で95%(19万年÷20万年)は狩猟採集社会でした。IT(コンピュータ)の活用は0.03%(0.006万年÷20万年)に過ぎません。圧倒的に狩猟採集社会の期間が長く、他の動物と同様に人間はその環境に適応するように世代を進化させてきました。19万年かけてです。狩猟採集社会とはどのような社会だったのか?大雑把なイメージしかわかりませんが、
(⇒は今)
今の時代(社会)とはかなり異なる時代(社会)が見えてきます。今の時代(社会)の"今"はいつからとするのかは難しいのですが、社会(生活)環境を著しく変化させたのは数百年・数千年のレベルでしょう。数百年と数千年では隔たりが大きく感じられますが、人類の歴史20万年(200,000年)の目盛りで見れば、両方とも一瞬です。日本で水田稲作による定住生活が遅くても2,400年前には始まったといわれているので、それを無理矢理持ってきたところで先ほどの俯瞰の3番目に
≫ 脱狩猟採集社会(生活) 約0.24万年(2,400年)
となるだけです。1.2%(0.24万年÷20万年)、圧倒的に狩猟採集社会の環境が人間の進化に影響してきた事がわかります。
すなわち人間は今の時代(社会)には適応していない動物だということです。先ほどの狩猟採集社会のイメージの8番目、
・生き延びるためには注意散漫で、周囲の危険を常に確認しなければならない
この時代、いかに身に迫る危険を素早く察知し、いかに早くその危険を避ける行動に移れるかが生き延びるために必要で、それに適応するように19万年かけて人間は進化してきました。特に脳の進化がキモとなります。脳が危険を察知してすぐに行動できるように、コルチゾールとアドレナリンを放出する指令を出すのですが、人類の歴史上危険(脅威)に結びつくのはポジティブな感情よりもネガティブな感情が多かったため、ネガティブな感情につながる情報に敏感となった考えられます。"悪いニュース"に対する興味が"良いニュース"の興味よりも高いのは、19万年に及ぶ人類の進化の結果ということです。今の時代は"悪いニュース"をある程度無視しても生き延びられますから、もっと"良いニュース"に興味を持てれば豊かな気持ちで生きて行けるようになるでしょう。そのように進化(変化)するためには、これから19万年必要なのかもしれません。すなわち『スマホ脳』では、「人間は現代社会に適応するようには進化していない」とありましたが「人間は社会の変化に適応するように社会の変化と同じスピードでは進化できない」ということなのかもしれません。
今回引用した『スマホ脳』、面白いです。あまり書くとネタバレとなるのでやめときますが、本のカバーに書かれていることを紹介します。
ちなみに"スマホ脳"であって、"IT脳"や"デジタル脳"ではないことも注目点です。スマホがIT(デジタル)機器の中でもやっかいな代物であることを示唆しています。本の主軸に流れているのは、先ほどから触れている「人間は現代社会に適応するようには進化していない」ということです。人間がスマホを真に使い熟すためには、スマホが与える影響と、狩猟採集時代の人間の特徴をバランスさせる取り組みが必要となります。現代人の特徴とのバランスだけではないということです。今回のコラムのきっかけでもあった「情報のバイアス」を考えるときに、今の時代のさまざまな要素だけでなく、19万年かけて進化した人間として根本的に持ち合わせているバイアスの要素(今回は"悪いニュース"への本質的な興味)にも目を向けないと、真の意味でのデジタルとの共存を迎えることは出来ない気がします。我々は19万年の進化の最先端にいる、という現実から逃げることは出来ません。
何しろITの進化・浸透は「19万年と0.006万年の出会い」なのですから。
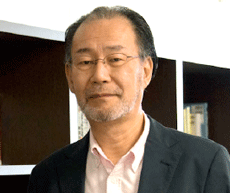
技術士(電気・電子部門)
永倉正洋 技術士事務所 代表
一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事
1980年 日立製作所入社。
システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。
2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。
2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。
2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。
2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。
2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。
2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。
2020年 日立アカデミーを退社。
永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。
お問い合わせ