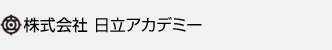-「使う」と「使いこなす」-
2014年11月21日'ひと'とITのコラム
前回のコラムでご紹介しましたが、筆者永倉の愛読書は『ゴルゴ13』。皆さんも普段意外なところから、ものごとのヒントを得たり、アイデアが湧いてくることがあると思います。永倉の場合は、主人公の言葉から意外な気づきを得たようです。
前回のコラムで《愛読書》としてゴルゴ13に触れました。色々気づかされる劇画なのですが、今回もこの気づきから一題。
ストーリーはIT産業振興で国力を高めようしているアイルランド共和国が舞台で、民族問題で対立する集団がハッカー中心にIT企業を襲撃して世情不安を起こそうとしているところから始まります。このハッカーを見つけて解決する仕事をアイルランドの首相からゴルゴ13が受けるのですが、ITで管理されている首相のスケジュールデータやゴルゴ13のクレジット情報、空港で映されるゴルゴ13の到着映像など、ハッカーには筒抜けとなることを敢えて隠さず、ハッカーをおびき寄せるように仕向けます。このときの彼の言葉、「ITが万能と思っている人間は、ITに疎い人間を下に見て馬鹿にするものだ。」「ITを万能と考えている人間は、ITを駆使して得たものを正しいと信じ込み疑わないものだ。」等々・・・
さて、ここから見えてくるものは一体何でしょうか? 技術を過信するな、溺れるな、はダイレクトに見えますが、私は「使う」と「使いこなす」の違いが思い浮かびました。
「最近のシニアはスマホを使える人が増えてきており、若者はスマホを使いこなしている人が増えている」と言えますが、「使う」と「使いこなす」の違いが重要なのではないかと感じます。では「使う」と「使いこなす」の違いは一体何なのでしょうか?まずは大辞林を調べてみると「使う」は『①ある目的のために物や体を利用する。②物を、それ本来の用途に用いる。』とあるのに対し「使いこなす(使い熟す)」は『使い方を心得て、十分に活用する。能力・特長などを十分に発揮させるように働かせる。』とあります。スマホを「使う」状態とは、音声通話やメールなどの機能を与えられたまま利用していることです。「使いこなす」状態とは、スマホの機能が生み出す価値の真偽を吟味し、自らのあらゆるシーンに溶け込ませ、さらに状況に応じたさまざまな活用形態をその人なりの工夫で柔軟に生み出し続けている状態です。すなわち「使う」という状態はその道具が"主役"であり、「使いこなす」という状態は使う人が"主役"と言えます。これは一見ITの知識が高い人が「使いこなせる」と見えます。しかしゴルゴ13が指摘していることは、ITの知識が高い人ほど技術主導に陥ってしまい、「使う」状態になりがちだということです。真の意味でIT人財がITを「使いこなす」ためには、ITを使う人の視点に立つ顧客志向とIT洞察力を発揮する意識を強く持ち続けなければなりません。
人は与えられた環境にそのまま埋没するのが最も楽です。ITが社会の基盤として「見えないIT」となっている現在、ユーザは与えられた環境を鵜呑みにしなければ、面倒臭くて使おうとはしないでしょう。すべてのユーザがITの真の価値を享受するためには、ユーザが知らないうちに「使いこなしている」という状況を作り出すIT環境が求められます。それを実現するIT人財は自らの姿勢と創り出す価値の双方で「使いこなす」ことを意識しなければならないのです。
書いてみると、自分でもゴルゴ13からの示唆にかなりの無理矢理感があります。しかし、読んだときにこのことが思い浮かんだのも事実です。気づきとは必ずしも理路整然としたものではないのかもしれません。
社会生態学者と言えばドラッカーが有名ですが、私はゴルゴ13からも社会生態を学んでいます。前回のコラムでも使ったフレーズで今回も締めたいと思います。
『たかが漫画、されど漫画!』

技術士(電気・電子部門)
株式会社 日立アカデミー
主幹コーディネータ
一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事
日立製作所でシステムエンジニアリングの経験を経て、2009年に日立インフォメーションアカデミー(現:日立アカデミー)に移る。企画本部長兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。2011年以降、主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施を担当している。
お問い合わせ