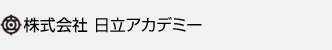-脳科学に関する研究論文から示唆されること-
2014年7月27日'ひと'とITのコラム
最近アメリカではIT企業の人工知能分野への投資が増えているそうです。また、日本でも人の感情を認識し、自分の判断で動くことができるロボットが開発されました。ITがどんどんヒト化しているように感じますが、はたしてそうなのでしょうか。私たちの身近にあるITの実態とは?!
最近、脳科学について少し勉強してみました(ヒトとしての自分が結構複雑で難解であることをあらためて認識しましたが・・・)。脳科学の研究で明らかにする方向性のひとつに科学技術文明をきづく礎は「人とは何か」を明らかにすることがあり、人の理解の鍵は、脳の情動系と学習・記憶機能の解明にあるようです。〈情動:怒りや喜びなどの感情のうち、急速に引き起こされ、その過程が一時的で急激なもの〉 人がITを使うという文明の進化と、これからのIT人財の育成のあり方の両面で興味が湧きました。
にわか勉強の結果、いくつか印象に残る項目がうかびました。
〔個性とは、脳の学習・記憶の特異性が決定するもの〕、〔人という動物の定義は、自分の存在が他の人から意義深いと思われているかどうか、という精神的判断基準を遺伝的に獲得されている動物〕、〔脳とは、"意欲"で動くコンピュータ〕、〔人類の進化に大きく貢献したのは、学習する能力ではなく、教える能力〕、〔「学習」とは、環境からの外部刺激によって中枢神経回路を構築する過程、「教育」とは、外部刺激を制御・補完する過程〕、〔情報化、個人化、効率化の加速という変化が脳にどの様な影響を与えているのかについては解明されていない〕、〔現在のコンピュータは人の情報を正確に取り扱うことはできないので、人がコンピュータに合わせるという状況。故に人が持つ個性が活かされない状況でコンピュータが人にかかわってくると、人の精神におよぼす影響は無視できなくなる〕。
これらの項目から多くのことが示唆されますが、ここでは二つの視点で見てみたいと思います。
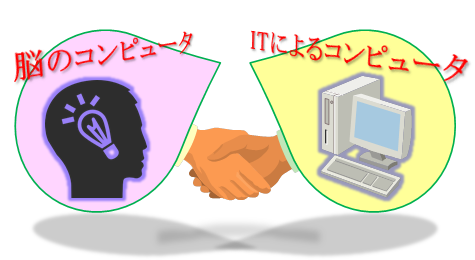
一つは、社会とITとの融合の形です。知識社会の到来と言われていますが、求められているのは人の「知」の発揮による価値の創出です。このために、人の数だけ存在する"脳のコンピュータ"を多様な個性(≒意欲)を活かして最適に稼働し連携させることができる社会の実現が求められています。この社会はITとの融合で実現されていくことになるのですが、脳科学の研究では"脳のコンピュータ"が"ITによるコンピュータ"に合わせなければならない状況が現出しています。主客転倒の状況で"脳のコンピュータ"の大きな特徴であり原動力とも言える個性が、活かされない社会となっているのかもしれません。
さらに、コンピュータはあらかじめ決められた手続きでしか動かないわけで、特に創造力や発想力といった人にしか成し得ない「知」の創出を打ち消してしまっている可能性もあります。"脳のコンピュータ"と"ITによるコンピュータ"の共存を、IT人財はもっと考えなければならないということです。思い付き的に言うと、プログラムが利便性の向上などを目的としてすべてを完結させるのではなく、"脳のコンピュータ"が動く場面を人が気づかないように(敢えて気づかせるのもありかもしれないが・・・)埋め込むことなどが必要なのではないでしょうか。
示唆されるもう一つは、IT人財育成の方向性です。従来から研修などによる学習転移では、受講者のモチベーションが重要であると言われてきました。脳科学の研究からも自分の存在意義が他人から認められていることを実感していることによる意欲や情動系への刺激などが大切であることが示唆されます。IT人財は他の技術者の活動領域と比べ、多種多様な拡がりの役割を持ちます。その役割そのものも時代と共に変化し続けています。また常にIT人財としての「知」の創出を求められ続けています。さらに社会でIT利用者も常にITとともに進化し続けていることなど、特異な特徴を持っています。かのキューリー夫妻曰く「科学技術は中立であり、善悪に関する価値は、全て使用する者の人間性にかかっている」、すなわち、技術者は「科学技術を発展させる前に、先ず、他人の立場に立てる心や多様性を受容できる心の育成、全ての人々へのリテラシー教育、創造性・意欲の向上、社会が激変する時代への対応を通じて人間らしさを確立することが必要」ということです。特に人類が創り出したITという今までに経験したことがない技術を扱うIT人財には、技術力だけでなく「人間力」の重要性が他の技術領域の人財以上に増してきています。すなわち、知識の習得という"脳のコンピュータ"への「蓄積」主体の研修だけでは足りないということです。意識や意欲、モチベーション、さらにはビジョン(生き様)といった"脳のコンピュータ"を活性化させる要素も含め、いかに知的価値の創出を促せば良いのか・・・ おそらく研修などのOFF-JTだけでは成り立ちません。新しい形のOJTや組織ビジョンとの連動なども含め、一人一人の個性を最適に活かすための施策や手法を立体的に開発することが必要です。私も自らの"脳のコンピュータ"を駆使しなければならない、とあらためて思っているこの頃です。大いに悩みましょう!

技術士(電気・電子部門)
株式会社 日立アカデミー
主幹コーディネータ
一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事
日立製作所でシステムエンジニアリングの経験を経て、2009年に日立インフォメーションアカデミー(現:日立アカデミー)に移る。企画本部長兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。2011年以降、主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施を担当している。
お問い合わせ