- デジタル時代だからこそ大切となる職場の"雑音" -
2024年8月21日'ひと'とITのコラム
今年5月に、自動車・二輪車の大手メーカーによる「量産に必要な認証"型式指定"の不正申請」という事件が明るみに出ました。また、7月には自衛隊で「特定秘密の不適切な取り扱い」や「潜水手当の不正」などの不祥事が相次いで発覚しました。このような事件が起こると、組織のトップが記者会見などで「事件の背景には、これらを正せない****があるので、それを変えていく」的な発言が多く聞かれます。この「****」の部分には、「組織風土(企業風土)」、「組織文化(企業文化)」、「社風」のどれかが入るケースが多いようです。
「組織風土(企業風土)」、「組織文化(企業文化)」、「社風」という言葉は、謝罪会見に限らずよく耳にすると思いますが、どんなイメージを持たれていますか? 恐らく「企業(組織)の中で暗黙的に共有している"雰囲気"や"空気感"」的な漠とした印象ではないでしょうか。通常は漠とした印象で捉えていても問題となることはあまりないでしょう。しかし昨今"ブーム"となっている「デジタルトランスフォーメーション(DX)」は、その漠然さを許してはいません。2018年12月に経済産業省が提示した『デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX 推進ガイドライン)』の中ではDXは次のように定義されています。
『企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。(下線は永倉追記)』
DXそのものについてはこのコラムでも『第34回 デジタル・トランスフォーメーションって何もの?』を皮切りに何回か触れてきていますのでここでは深掘りはしませんが、注目したいのはDXが『企業文化・風土の変革』を包含していることです。つまり、DXを推進するためには、デジタル(IT)の視点だけでなく企業文化・風土についての視点が必要であり、そのためには企業文化・風土の"漠然では無い"しっかりとした知見が必要ということです。しかし、DXの推進で企業文化・風土について語られている例はあまり見受けられないのも事実です(この辺が、DXレポート2やDXレポート3で "DXの誤解"が蔓延していると指摘された事にもつながっているのでしょう・・・)。
そもそも組織風土と組織文化とは何が違うのでしょう。ここでやっかいなのは、色々な文献や知見者の発信を見ると、微妙に異なっていることです。このため、いつものように辞書に原点を求めてみます。
"風土"と"文化"を広辞苑(第7版)で調べてみます。
風土:その土地固有の気候・地味など、自然条件。土地柄。特に、住民の気質や文化に影響を及ぼす環境にいう。
文化: (略) ③(culture)人間が自然に手を加えて形成してきた物心両面の成果。衣食住をはじめ科学・技術・学問・芸術・道徳・宗教・政治など生活形成の様式と内容とを含む。文明とほぼ同義に用いられることが多いが、西洋では人間の精神的生活にかかわるものを文化と呼び、技術的発展のニュアンスが強い文明と区別する。
この記述から"風土"は見えたり実感できたりする具体的要素(環境)で、"文化"は"風土"の影響を受けながら生じる物心(物質と精神)両面の成果(結果)と言えそうです。企業(組織)に照らしてみると、組織風土は、「当該組織の従業員のモチベーションや行動に影響を与える組織環境の特性」で、組織文化は「当該組織の中で従業員が共有している価値観や行動理念」と見ることが出来ます。ということは、組織風土はある程度明示的に認識できる要素で、組織文化はその組織に属する人の精神面などの暗黙的な要素を含むことになります。組織風土によって組織文化が醸成されるということですね。ただし、組織文化が広く醸成されることで、それが組織風土に影響を与えることもありそうです。冒頭に触れた謝罪会見の文言は、「組織風土を変えることで適切な(あるべき)組織文化を醸成していく」というのが正解なのでしょう。
組織風土に影響を与える要因にはどのようなものがあるのでしょうか。組織に所属していると否応なしに関わらざるを得ない"もの"や"こと"のほとんどが関わってきます。
まず、(A)「組織内で明文化された制度やルールなどによるもの」として、
・経営理念 ・経営計画 ・事業内容 ・組織のミッションやビジョン ・組織構造・体制
・人事制度 ・評価制度 ・就業規則 ・業務プロセス ・組織の運営方法 など
次に(B)「視覚化し難い所属している一人ひとりの心構えや価値観などに依存するもの」として、
・モチベーション ・エンゲージメント ・組織内の価値観 ・人間関係 ・信頼関係
・職場での相互協力の度合い ・ノウハウの蓄積や情報共有の仕方 など
が挙げられます。このほか組織が存在するために必要であったり、組織の存在で必ず創出される要素が関わってきます。先に触れたDXレポートでの「DXの定義」で、『業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し』とあるように、DXの推進は企業風土に深く関わる取組みであり、これを実現出来るのは「経営レベル」でしかないので、「経営の"変革"」と定義づけているのもわかります。
では、「当該組織の中で従業員が共有している価値観や行動理念」である組織文化はどのように醸成されるのでしょうか。前述の組織風土のうち(A)の「組織内で明文化された制度やルールなどによるもの」は、ある意味"静的"な要素です。それを元に人が(B)の「視覚化し難い所属している一人ひとりの心構えや価値観などに依存するもの」の要素で"動的" に活動します。この一人ひとりに芽生える心構えや価値観が組織内で共有されて根付いていくことで、組織文化の醸成につながっていきます。では具体的にどのように共有しているのか?業務の遂行というメインストリームで、さまざまな判断や取り組み姿勢などによって価値観や行動理念を共有しているだけでなく、所謂「職場の雰囲気」といったメインストリーム周辺のさまざまな場面で共有されているものも多くあります。
例えば
・言いたいことが言える雰囲気なのか ・助けあったり、アドバイスしあったりする雰囲気なのか
・上下関係が厳しい雰囲気なのか ・平等に尊重される雰囲気なのか ・楽しい雰囲気なのか
なども組織文化に大きな影響を与えています。最近就活の面談で「職場はブラックではないのか?」という不安からか、多くの学生が「御社の社風は?」的な質問をするようなのですが、彼ら彼女らが気になるのは「職場の雰囲気」という視点、すなわち組織文化なのでしょう。
では、DXの定義でも取り上げられる程、なぜ職場文化が重要となったのでしょうか?
特に日本の組織では、いくつかの要因が重なっていると考察できますが、大きく影響したのは"定型業務"一辺倒からの脱却です。日本は過去(20世紀末)に"ものづくり"で世界を席巻した成功経験があります。このとき組織の中で求められていたのは「高品質・低廉な製品を人が変わっても作り続ける」ための企業文化です。関係する人すべてが同じ業務を熟すことが求められますので、"定型業務"主体の組織風土だったということです。すなわちこの時代、あるべき(必要な)組織文化は業務プロセスという"骨格"に封じ込めていた時代なのかもしれません。そしてそれがうまく機能していたのも事実です。封じ込められていた、ということは多くの人からは組織文化という存在が見えていなかったということなので、組織文化の必要性や重要性は認識されてこなかったということになります。しかし、経営・事業環境が変わり、決まった価値の提供だけでは立ちゆかなくなりました。斬新な価値の提供が求められるようになります。すると、"定型業務"だけでは何も応えられなくなりました。一人ひとりがさまざまな工夫をしながら取り組む"非定型業務"の重要性が増大してきています。"非定型業務"の遂行は、"定型業務"の遂行よりも個人への裁量や責任などの依存度が高くなります。ここで大切なのは、各個人自らが安心して業務を進めるための方向性が明確となっていて、そのための環境が整っていることです。この方向性が経営ビジョン・事業ビジョンであり、環境が組織文化となり、俄然その重要性が認識されてきました。この視点でもう一度「DXの定義」を読んでみると、経営者に対して従来の"定型業務"の改善・改良を主目的としていた「データとデジタル技術の活用」だけではなく、個々の従業員が"非定型業務"を遂行できる環境を整えるための「データとデジタル技術の活用」と、それを前提とした企業風土に変革して、各従業員の価値を最適に創出する企業文化を醸成させることを提言していることがよくわかります。
しかし、「言うは易し」・・・
先ほど組織文化の醸成は、『所謂「職場の雰囲気」といったメインストリーム周辺のさまざまな場面で共有されているものも多くあります。』と書きました。例として、
・言いたいことが言える雰囲気なのか ・助けあったり、アドバイスしあったりする雰囲気なのか
・上下関係が厳しい雰囲気なのか ・平等に尊重される雰囲気なのか ・楽しい雰囲気なのか
などを挙げました。私も現役の頃、自分に直接関わることでなくても、職場で誰かが助けを求めている、誰かが褒められている、誰かが叱られている、誰かが困っている・・・等々さまざまな"雑音"を見聞きするからこそ「職場の雰囲気」を感じることが出来ていました。しかも、その"雑音"の方が、メインストリームで実感することよりも組織文化につながる要素を広く・深く実感できていたように思います。コロナ禍を経て、デジタルの活用の具現化で、リモートワークやフリーアドレス化が大きな流れとなっています。メインストリームの業務はどうにか熟せるように思いますが、逆にそこに絞っているからこそ実現出来ている面もあります。すなわち絞るために切り捨てているものもあるということで、その中に先ほど触れた"雑音"があります。DXの推進で「データとデジタル技術の活用」を前提として企業風土・文化の変革を促しているにも関わらず、デジタル技術の活用が組織文化の醸成を阻害する可能性があるという矛盾を抱えているとも見えます。
デジタル前提の「 "雑音"を共有出来る新しい仕組み・仕掛け」も、DX実現の要素として真剣に考えなければならない時代を迎えています。
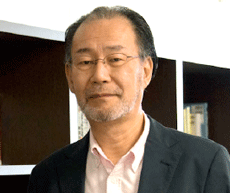
技術士(電気・電子部門)
永倉正洋 技術士事務所 代表
一般社団法人 人材育成と教育サービス協議会(JAMOTE)理事
1980年 日立製作所入社。
システム事業部(当時)で電力情報、通信監視、鉄道、地域活性化などのシステムエンジニアリングに取り組む。
2003年 情報・通信グループ アウトソーシング事業部情報ユーティリティセンタ(当時)センタ長として、情報ユーティリティ型ビジネスモデル立案などを推進。
2004年 uVALUE推進室(当時)室長として、情報・通信グループ事業コンセプトuVALUEを推進。
2006年 uVALUE・コミュニケーション本部(当時)本部長としてuVALUEの推進と広報/宣伝などを軸とした統合コミュニケーション戦略の立案と推進に従事。
2009年 日立インフォメーションアカデミー(当時)に移り、主幹兼研究開発センタ長としてIT人財育成に関する業務に従事。
2010年 企画本部長兼研究開発センタ長として、人財育成事業運営の企画に従事。
2011年 主幹コーディネータとしてIT人財に求められる意識・スキル・コンピテンシーの変化を踏まえた「人財育成のための立体的施策」立案と、 組織・事業ビジョンの浸透、意識や意欲の醸成などの講演・研修の開発・実施に従事。
2020年 日立アカデミーを退社。
永倉正洋技術士事務所を設立し、情報通信技術に関する支援・伝承などに取り組む。日立アカデミーの研修講師などを通じて、特に意識醸成、意識改革、行動変容などの人財育成に関する立体的施策の立案と実践に力点を置いて推進中。
お問い合わせ